
最近の息子は、どうも学校が嫌な様子が見えています。喉のチック症状が見られるようになりました。過度のストレスがかかっているのだと思います。また、強迫性障害からの確認行動が増えています。強迫性障害の症状が厳しく出ている印象です。知的障害・自閉症の子の二次障害の現実について知りたい方は読んでみたら参考になるかもしれません。
「強迫性障害が強くなっている」その症状と原因
最近の息子は、強迫性障害が強く出ているように感じます。どんな強迫性障害の症状が出ているかというと…
- 確認行動が多い
- 喉に違和感を感じている
- 怒りっぽくなっている
こういったことが出ています。
根本的な原因は、学校でのこと。厳しい(指導)躾が原因だと考えられます。正直には、身バレの可能性もあるので細かく書けないのですが、うちの子供の場合、(間違って伝える、大げさに伝えることがあるので)あんまり当てにはできないのですが、言葉で伝えてくれるので、学校での人間関係が原因だと考えられます。あまりにも厳しい現実が言葉になって現れます。僕は、学校全体に改善を求めるほどに重要な案件だと理解をしています。それで、先日、とうとう学校と話し合いにいきました。でも、少し遅かったと思っています。
「学校が辛い」息子はよく口にするようになりました。
そうなると、うちにいても不安が強くなってくるのです。
物依存が強い息子ですので、物に対しても不安が強くなっています。うちの息子が大切にしているものは…
「海外キャラクターのぬいぐるみ」「ペガサスの飾りもの」「ココメロンのおもちゃ」なんですが、そういったものに対しても不安が強くなっているようです。つまりは、「大切にしているもの」に対しての依存が強いので、「それらが無くならないか?」「汚れちゃうんじゃないか」と不安になるのです。その際には、起こりえないことまで不安になっています。例えば、
- 「勝手に部屋から出て、廊下に落ちていないか?」
- 「冷蔵庫の中に大切なものが入っていないか?」
- 「ゴミ袋に入っているのではないか?」
そんな不安を抱いて、それが過剰に不安なのです。
だから…息子は妻に確認していきます。「ねえ、汚れてない?」と聞きます。
妻は、すぐに答えます。「大丈夫よ」と。
でも、その後にまるで聞いていなかったように、もう一度聞いてきます。
過剰に不安なために、一度、「大丈夫」と言われても心配が拭い去れないのです。
自分の目で見て済むことのはずなのに、自分の「目」すら疑っているのです。
そして、最近ではそれらが更に加速しています。
「自分のものを誰かが触るのは嫌だ」まで広がっています。
大したものでなくても、大切にしているものでなくても、「自分のものを見るな」「自分のものを触れるな」に変わってきているのです。それは、妹まで進んでいます。妹が正しいことを学ぶのに阻害している状況にまで発展しています。どういうことか?
「自分のエプロンを見ないでよ」と言い出して、娘が触りだすのではないか?と不安になっているのです。娘からしたら…なんで?となるでしょう。「そんなこともダメなの?わたしのこと、嫌い?」と不安になるでしょう。それを注意するのなら、息子に対して、「そんなことを言うな」と注意すべきでしょうが、それもまた、別の問題の引き金になりかねません。
でも、その要因は、実は、「学校での生活の中にある」のがすぐに分かりました。
強迫性障害の要因は、「根本的な要因がある」ことが殆どです。
物が不安で確認行動が多いわけではない。
当然に不安症が強まっているだけで、色々な要因があるとは思います。
でも、強迫性障害の場合は、根本の原因を解決に近づける必要があります。
手洗いが止まらないのは、手が汚いと不安なだけではないんです。
物がなくなったか不安なのは、それだけが原因ではないんです。
うちの息子の場合は、根底には、「学校が怖い」という原因が潜んでいました。
うちの息子のいう言葉をどこまで信用するのか?その点には不安もありますが、でも、学校に行きたがらない息子を見ていて、それらは真実に近いことなのだろうと、息子からの話で、色々な事々に、がっかりもしました。(詳しく書けなくてごめんなさい)
息子の状況について学校との話あい
僕は、妻と一緒に、モニタリングの依頼を、相談支援専門員の方にお願いしました。
僕は、学校の先生と向き合う時、いつだって「先生にお任せします」とお願いしてきました。
先生方は、特別支援学校に勤務をして、一生懸命子供たちを見つめてくれている人たちだから、多少のズレがあっても、それで良いと思っているのです。
ただ、今回は、少し、問題がありました。
正直、親として、「ここまで、つっこんだ話をするのは、モンスターペアレントと思われるのでは?」と不安に感じるものですが、それでも、事が大きかったので、僕が主体となって、先生との話を進めました。
それでも、「ご理解を得られたのではないか?」と思っています。
というか、あの話(しつこいですが、具体的にかけず、申し訳ないです)をして、理解が得られないよだったら、次のステップを考えねばなりませんでした。
具体的な子供の話として、先生の指導方針に口を出すのは、本当に嫌でしたが、今回は深くお話をさせて頂きました。詳しくは書けないのですが、「何を伝えたか?」だけは記載しておきます。それは、
息子の40歳になった頃の、僕が生きていない世界の「サービス等利用計画」でした。
僕は、「息子の指導にそこまで焦らなくて良いのです」を先生に伝えたかったのです。
二次障害をより難しくしてまで、就労支援に執着しないし、学校に通う必要もない。
それを伝えたかったのです。
息子は、ゆっくりと、25歳までに成長してくれたら良いのです。
その際に、施設やグループホームで、僕という親がいない世界で、息子が一回でも多く「笑う」ために、「何が必要なのか?」学校の教育はそこに向かうために「何が必要なのか」が考えた指導をすることが大切です。
僕の息子は、中等度の知的障害があり、強い自閉症。強迫性障害があります。
学校教育プログラムで必要とされることは、本当に必要なんでしょうか?それを成しえるために、焦る必要があるのでしょうか?案外に、みんな(先生、支援者、保護者)は、子供たちが「親亡き後」に「どこで生活し、どんな生活をして、どんな人たちと向き合っていくことになるのか」のイメージの欠如があるように思います。
僕が生きているうちは、息子の笑顔を引き出せる
でも、僕がいなくなったら?妻がいなくなったら?
「どんな息子ならば、支援者に愛されるのか?」
残念ながら、容姿は大人になり、子供の頃のような可愛さはなくなります。
年齢が増した息子の仕草や、考えが可愛く感じられても、「慣れれば」面倒に感じる支援者も出てくるかもしれません。
息子が将来、笑って生活をするために、何が必要なのか?
その考えなしに、「今」の教育プログラムに執着するだけでは、
息子の本当の意味での幸せにはたどり着けないのではないか?と僕は考えます。
だから、40歳の頃の息子の「サービス等利用計画」を作成して、一緒に何が必要かを考えて貰ったのです。
だから、僕は、この気持ちを、先生に伝えていったのです。
それから、数日が立ち…(まとめ)
今は、息子と先生の関係性が少し変化し、学校での大きな不安は和らいだようです。しかし、二次障害としての強迫行動はそう簡単には落ち着かず、引き続き物依存の様子が見られています。そう簡単にはいかないものです。
それでも、一歩踏み出し、息子にとって本当に必要なものは何かを問いかけることができたと信じています。知的・自閉症の子の二次障害は、環境からのサインです。 もし同じように悩んでいる方がいたら、「親亡き後」の視点から、根本的な原因に目を向けてみてはいかがでしょうか。そして、長い目線で、子供の成長がどうあるべきかを考えていってはどうでしょうか。
父としての模索は続きます。が、親亡き後の息子の笑顔のために、僕は日々を大切にしていきます。
強迫性障害について、興味のある方はこちら↓
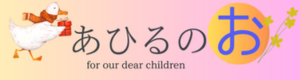
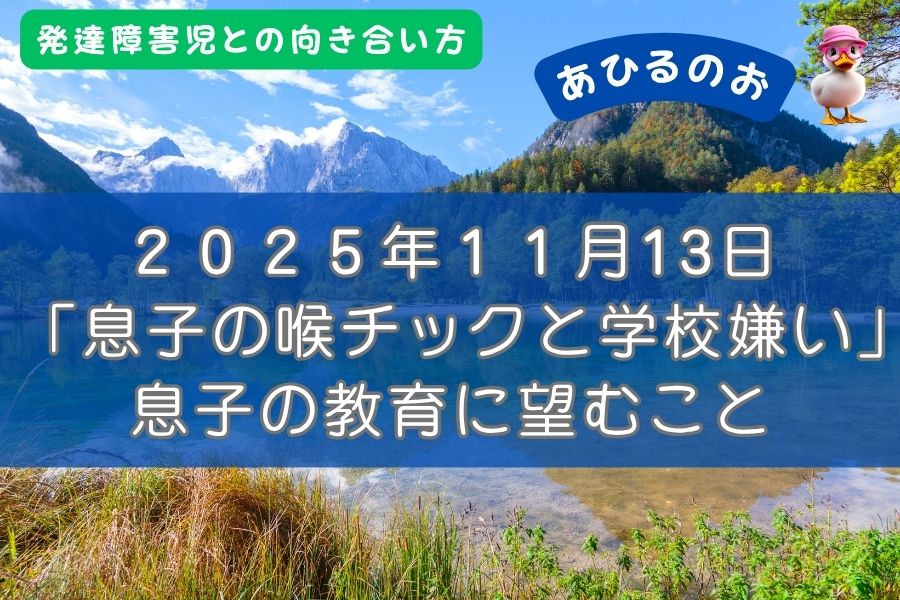


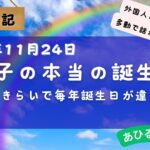
コメント