僕は、発達障害児の支援者であり、障害者の支援者であり、高齢者の支援者です。
現在、福祉の幅を広げて、すべてをやっているんです。
つらい😭
そして、僕は、障害児のパパです。保護者さんなんです。
そんな中で感じることが一つあるわけです。
高齢者介護において、最後って見えるんです。
自分が何をすべきかが明白です。
常に結果を意識しています。
それで、そこにいる人がどんな気持ちで生きているのかを見つめていくと、
自分があるべき姿が見えてくる気がするのです。
そして、障害児分野において、
僕が感じていることは一つです。
「結果を最後まで見た人がいない…」
ということです。
もともないことなんです。
それは分かっているのです。
理論は理論なんです。
どんな支援者でも、一人の人の人生をすべてを追いかけた人はいません。
5歳で出会った児童を50歳まで見つめた人がいるだろうか?
結果とはなんぞや。
支援者で、よく理論・理屈・助言を並べる人がいます。
自分も一緒。
でも、その結果が良い結果であっても、「その支援者の影響で〇になった」と言い切れることがありません。
だから、僕は、アドバイスはできる限りしたくない。
できることはきっと、保護者に対する「励まし」や「エール」なんだと思うわけです。
Instagramに、X、相談関係、色んな場面で「子育て」についての療育的な支援方法が並びます。
そして、僕も時折、見て回ります。ノウハウに、療育方法に、〇〇法。
「私は、息子を叱ってました。怒ってました。でも、変わった…それは〇〇を学んだから」みたいなものも良くみかけます。相談を自分もやりたいけれど、ちょっと価値観が違う。
僕は、親に叱られた経験が沢山あります。
でも、自分の親が大好きです。感謝もしています。
叱られた経験がそれなりにある自分は、一応、健常者と言われています。発達特性があったから、なかったから…叱られたから、叱られた経験がないから…それだけで、「子育て」は上手くいくのでしょうか?
何が結果をもたらすのか?
人との出会い?
失敗から学んだ?
環境?
僕の頭の中は、結構に真剣です。
ぐるぐる回って、分からなくなる。
でも、力なく生きている高齢者を見ます。その人は、子育てをし終えて、それから、色んな心配を背負って生きてきた人たち。力つきたように、介護者に言われるがまま、行きたい所にもいけず、出された食事を食べ、出されたお茶を飲み、適当に流されたテレビがあるけれど、見ているようで見ていない。そんな生活。
うちの子は、あんな感じになるんだろうか?
ふとそんなことを考えた時に、何が幸福なのか?も頭の中をぐるぐる回ります。
結論。
僕は、療育に重要性を見いだせていないのです。
支援者を見つめる時に、その人のテクニックには目が向きません。
温かいか否か。それだけを見つめてしまいます。
知識豊富な人がダメなんじゃなくて、
それよりも、優先順位が高いのが、温かいか否かなんですね。
僕も支援者です。
偏食の対応の仕方とかパニックの対処、学校へ行けない子の気持ちなどなど、質問を沢山、受けてきました。
でも、あんまり、アドバイスをしようは思えなかったんですね。聞かれればする。でも、僕は、アドバイスをしている時、着心地の悪い洋服を着せられているような気持ちでした。
ただ、保護者さんには「これだけはやめようね」というのは伝えるべきだとは思っていますが、よりよい人生の構築を考えた際に、療育や支援では解決できないことが多いのです。
それが、最近、一番、寂しいことなのです。
だって、誰か一人でも支援者の方で、
子供が50代になって幸せそうか否かを見た人はいるのでしょうか。
どう幸せになったか?です。
「〇〇くんに、当時、僕がこういった、こう療育したから、ほら見てごらん、50歳の彼にこんな影響力を持ったんだ」と誰が言えるのでしょうか?
もちろん、そこまでの責任は持つ必要もないですし、
その結果を知れる人がいないのは当たり前です。
そして、今の療育を考えた時には、
「支援者に愛される」とか「施設に入っても安心」とかが基準になりますが、
それって本当に幸せなんでしょうか?そう思ってしまうのです。
実は、もっと力を発揮することが出来たのではないか?
何が違うのか?もっと革新的な方法があるんじゃないか?
それは、親として、
「自分の息子を、じっと見つめている時」
に感じるんです。
自分の子には、施設で力なく、うずくまっているだけの様な生活をさせたくない。
「もっと可能性がある」って信じたい。
そのきっかけは療育とか、そういうものではないのかもしれません。
なんだろう?きっかけ。
どんなことを伝えていけば良いのだろう?
ごく当たり前の療育を行えば、行うほど、可能性を狭めているような気がしてしまいます。
今は、「支援はこうあるべき」が強すぎるように感じるのです。
だって、みんなが同じ勉強をするから。
個別性というけれど、その土台は、統計学です。
そして、心理とか療育とか、声掛け方法とかが並びます。
それって、たぶん枝葉でしかない。
漠然と、あいまいに、凄くそんなことを感じるのです。
今日は、このブログサイトの根幹を揺るがすような話を書きました。
また、自分のInstagramや、Xなんかの根幹も揺るがすようなことを書きました(笑)
また、支援者さんに対して、失礼な内容でもあるかと思います。
けして、支援者さんを侮辱しているつもりはないのです。
ただ、保護者と支援者の両方を経験していくと、親亡き後の人生を「〇〇に生きるべき」と決めつけてしまうのが怖いだけなんですね。知識も重要だとは思っているのです。
ただ、僕がかかわった子供たちにとって、
より幸福を掴んで欲しいと心から願うのです。
「もっと、君たちは出来る」
そのためには、こんな考えを知っておけ…そう伝えられなかったな…ごめん。そう思います。
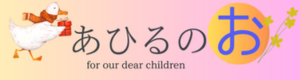
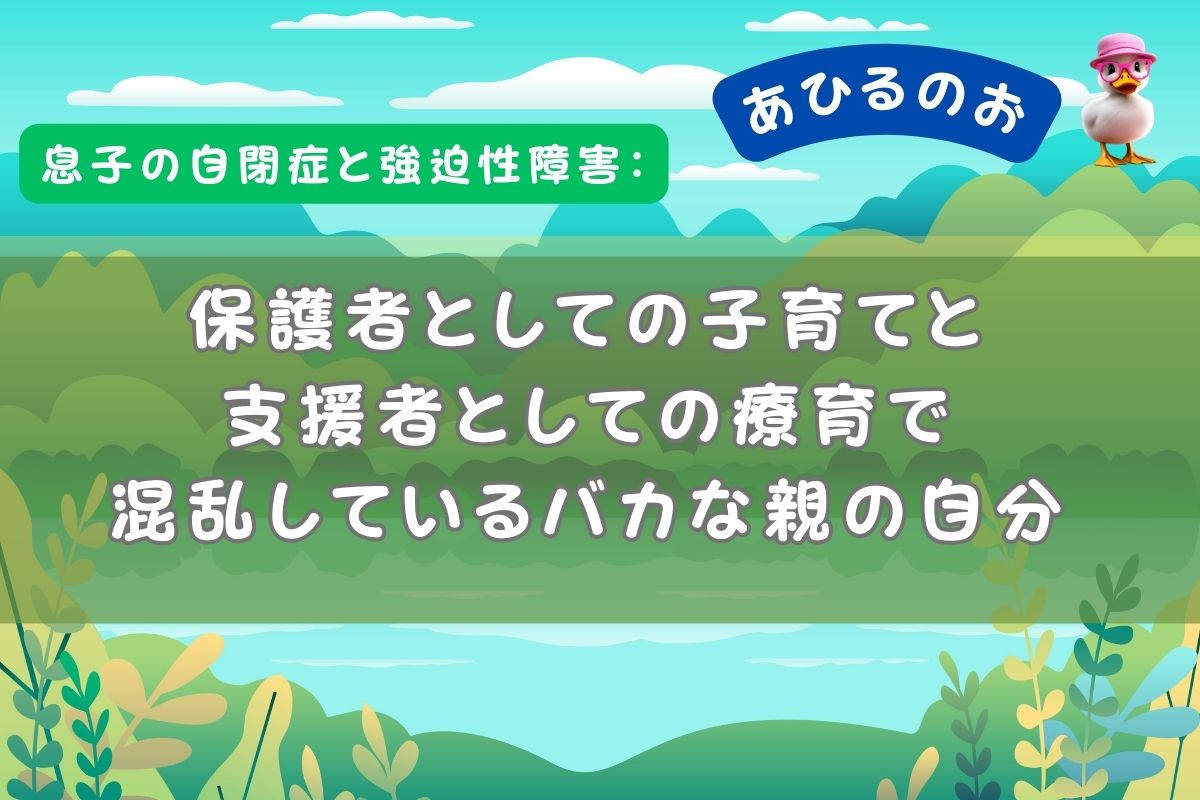

コメント
あひるのおさん、ソニック情報をお伝えします♪
⒈ ソニックレーシングのグッズがドンキホーテで9月27日から発売!
(税込2,000円購入ごとに特典ミニカードプレゼント) https://l.smartnews.com/m-6bCVQZXO/GcrGeJ
⒉ 「ソニック」と「初音ミク」のコラボ企画に新曲が登場
(ピコピコハンマーが武器のエミーちゃ
んをテーマにした曲)
https://l.smartnews.com/m-6bCWepfG/0nriU7
⒊ソニックのLINEスタンプ↓
https://l.smartnews.com/m-6bCVydnq/FX7GTe
いつも、ありがとうございます。息子にも伝えておきますね。ママも助かっています。この前に教えて頂いた、栃木のイベントにも行ってあげたいと思ってます。本当にいつもありがとうございます!