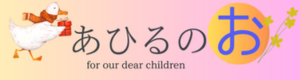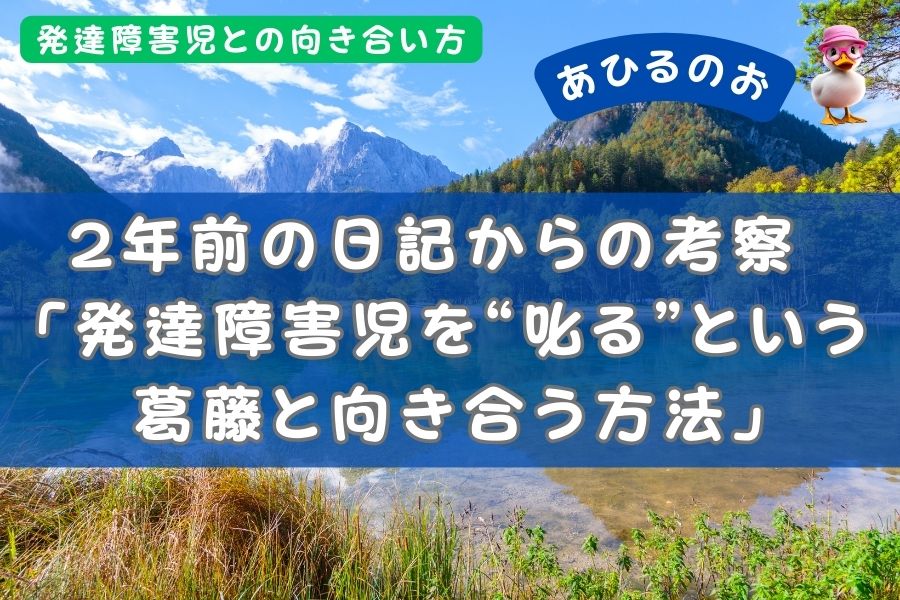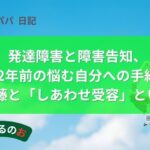こんにちは。この記事を読んでくださっている皆さんは、もしかしたら今、お子さんを叱ってしまったことや、子育ての中の終わりのないように思える葛藤(ジレンマ)に、深く悩んでいらっしゃるかもしれません。その葛藤は凄くつらいものです。だからこそ、この記事を読んで貰えたらと思います。
こんにちは。今、この記事を読んでくださっているあなたは、もしかしたらお子さんを叱ってしまった後、深い自己嫌悪に陥っていませんか?
「子どものためを思っての行動だったはずなのに、どうしてこんなに苦しいんだろう…」
そんな終わりのない葛藤(ジレンマ)は、僕もまた、日々感じていることです。この記事は、2年半前の僕が経験した、ある出来事から生まれました。当時の僕は、自分の行動が正しかったのか分からず、ただただ自分を責めていました。でも、時を経て、あの日のことを振り返ることで、「叱る」という行為の本当の意味に気づかされました。
これは、かつて迷っていた僕自身と、今同じように悩んでいるあなたへのメッセージです。
2年半前の日記を読み直して
「放課後等デイサービス 叱るということ」(2年前の日記)
この話題から文章を作ることになるのがつらいですが、この話題から作っていきたいと思います。
僕は、息子が障害があることと高齢者福祉をしている自分に常にジレンマを感じてきました。
自分は福祉が大好き人間です。
高齢者介護は本当に天職だと思って仕事をしていました。
しかしながら、常に「ジレンマ」に駆られていたのです。
「息子が障害があるのに高齢者介護をしているの?障害者の福祉をするのが親心でしょ?」
その疑問が常に頭にあったのです。
僕は高齢者介護が大好きだけれど、息子の障害を背中に背負って何か悪いことをしているような…そんな感覚だったのです。その後ろめたさを払拭するかのように、「放課後等デイサービス」の職員に転職したのです。転職しても高齢者介護の時と同じように感じることがあります。つくづく思う事は、「福祉というのは常にジレンマを感じる仕事だ」ということです。
「少し困りごとがある人々の集まりである福祉現場」には、人と人が絡み合う葛藤がつきものです。
福祉職というのは、「誰かによくしてあげると誰かが不満や悲哀を感じる」というジレンマと常に向き合う必要があります。このことをどう乗り越えていくかこそが福祉の醍醐味であり、福祉職に就く人の『仕事ができる人と出来ない人の差』だとさえ思っているのです。
常に、その葛藤と向き合うには、「自分のポリシー」「どうしても曲げられないこと」「大切にしている倫理観」が必要なのです。すべての人を大切にする。それはとても難しいことですが、それがとても大切なのです。
思えば、「息子が障害があるのに高齢者介護をしているの?障害者の福祉をするのが親心でしょ?」この葛藤も僕が福祉をしているからこそに巻き起こるジレンマでした。自分でいうのもなんですが、僕は福祉が大好きだから、このジレンマにぶつかったんだと思っています。
さて、本題ですが、僕は昨日にある生徒をしかりました。
そこには葛藤があるのです。
叱るのがこんなに自分の精神を苦しめることはありません。
「叱っちゃだめ」そんなことは分かっているのです。
でも、福祉だからこそ、常に巻き起こる葛藤(ジレンマ)がつきまといます。
例えば、帰りの送迎である市営団地に生徒2名を送ります。
その内の一人A君が「お腹と頭が痛い」と言ってしゃがみ込みます。
その時に、別の生徒Bさんが「おうちに帰りたくない」と言い出します。
叱ることもなく、「どうして帰りたくないの?」と聞きます。
すると、「あの時、○○くんが私のことをバカにしたから」と始まります。
実際には、バカにして言った言葉ではないので「バカにはしていないよ。大丈夫だよ」と伝え、「今は○○ちゃんがお腹と頭が痛くて」と理由を伝えますが、「そんなのどうでもいい。私は動かない!お前は向こうにいけ」となるのです。その後ろで泣きながらA君が「頭がいたい。はきそう…」というのです。
団地に住んでいるので、エレベーターですぐに送れるわけですが、Bさんを置いていくわけにもいかないのです。再三の説得にもBさんは応じません。ない頭を使って、A君の状態とのジレンマを感じながら、「叱るか諭すか」の選択に自分はさらにジレンマと葛藤を重ねていきます。
そして、「あと少しで怒るしかなくなるよ」と伝えて、僕は叱るを選択をしたのです。
叱られたBさんの気持ちを考え、A君を送ったあとにBさん宅を訪れて僕はBさんに謝ります。
「叱りたくなかったけれど、君の気持ちを考えたら叱りたくなかった。ごめなさい」と大人に謝罪をするようにしっかりと頭を下げるのです。そして教えます。「お友達が頭が痛い。体調が悪い時には、自分の時のことも考えて協力しなきゃだめだよ」と。そして、帰る間際に「君が大切で、君が大好きだよ」と言って帰るのです。
そして、そういった「叱る」をする子は限られます。
どうしてもこれから社会にでることになる支援級クラスの子でトラウマが残らない子たちです。
叱る時には必ず「君が大好きだから叱ります」と伝えています。
怖い顔をしますが、最後は必ず笑い「君が大切です」と伝えるようにしています。
「かっこいい男になれ」「正しい判断ができる人になって」そうも伝えます。
それから、自宅に戻り、「自分が正しかったのか?」と再びジレンマに駆られます。
でも、僕はそのジレンマの中に必ず、自分の信念を持つようにしています。
「すべての生徒を大切に想うこと」という信念です。
それでも、自己反省や葛藤に襲われます。あれで、正しかったのだろうか?と。
僕は間違いも起こします。でも、その時は、子供であれ、しっかりと謝ります。
プライドもくそもない…そう言われるかもしれません。でも、僕には生徒は大切な「人」たちです。
僕に喜びも悲しみも苛立ちも与えてくれる子供たちです。
僕が与えているのではなく、僕が彼らからギフトを貰っているのです。だから…
さて、具体性があったかなかったか、今日はこんな話で終わります。あんまり頑張ると続かないから(笑)
2年前の日記の考察 「叱る」ということの葛藤
今から2年前、僕は福祉の現場で経験した葛藤について、このブログに綴りました。
当時の僕は、自分の行動が正しかったのか分からず、ただただ自分を責めていました。正しいと思いこもうとしていたところもあるかと思います。
あの時どうしたら良かったのか?と悩むわけです。
しかし、あれから2年の時が経ち、当時のことを振り返ることで、「叱る」という行為の本当の意味に気づかされました。この記事は、かつて迷っていた僕自身と、今、同じように悩んでいる発達障害児の保護者さんへのメッセージです。
2年前の僕が直面した「終わらないジレンマ」
当時、僕は息子に障害があるにもかかわらず、高齢者福祉に携わることに後ろめたさを感じていました。そのジレンマから逃れるように転職した放課後等デイサービスでも、やはり福祉の現場には常に葛藤がありました。
誰か一人に尽くせば、別の誰かが不満を抱く。 そのことを肌で感じながら、僕は「すべての人間を大切にする」という、一見シンプルでありながら、現実では、「最も難しい信念」を掲げていました。しかし、この信念こそが、葛藤にどう向き合うかを僕に問いかけていたのです。
あの日、僕は生徒を“叱る”しかなかった
あれは帰りの送迎での出来事でした。
一人の生徒A君が突然の体調不良で苦しむ一方、もう一人の生徒Bさんは「お家に帰りたくない」と頑なに座り込んで動こうとしませんでした。体調の悪いA君を最優先すべきか、それともBさんの気持ちを尊重すべきか…。あの時、僕は二つの正しさの間で激しく葛藤していました。
Bさんをなだめても状況は変わらず、時間だけが過ぎていく。頭痛と吐き気は酷くなるようで、A君が泣き出します。「帰りたいよ」と。苦渋の選択の末、僕は「あと少しで怒るしかなくなるよ」と告げ、Bさんを叱るという道を選びました。でも、今ならどうするか?
たぶん、叱りません。
その上で、A君のお母さんに電話をして、下まで来てもらう選択をすると思います。
ただ、あの時に、その選択が僕にできたかどうかは分かりません。
とっさのことでしたから。そんなすぐにでも思いつきそうな対応を思いつかない。情けない所ですが、その時は、焦りの中にあり、「叱る」という判断しかできなかったのです。
それと、一つ…
「友達が具合が悪い」というその状況下で、自分の不満だけでA君を無視して、自分のことだけを訴えるBさんの…その価値基準。それを、放置して、「何が正しいのかを教えないことは、善なのか」と言われると、それは違うように思います。叱らないにせよ、その点をBさんには教えていく必要があるとは思っています。
2年前の僕には、この「叱る」という選択が「失敗」のように思えることもありました。
ですが、今なら分かります。あの時の僕に、A君を連れ、Bさんを置き去りにするという選択肢はなかったのです。
叱ることの後、本当に大切なこと
あの時、叱った後の僕を動かしたのは、ただ一つの思いでした。
「Bさんの心に、叱られたことだけが残ってはいけない」
僕はA君を送り届けた後、すぐにBさんの家を訪ね、深く頭を下げて謝罪しました。
「叱りたくなかった。君の気持ちを考えたら、叱りたくなかったんだ。ごめんなさい」と。
それは、その時の選択として、僕は正しかったと思っています。
生徒とか先生とかの立場の問題ではなく、自分が悪い事をしたと思ったら、謝る。
それは、「謝ることの大切さ」を生徒に伝えるためにも必要なことだと僕は思うのです。
保護者さんでも、緊急事態の時、時間がない時などには、自分が思っていたことと違う選択(例えば、叱るとか、脅すとか)をしてしまうこともあると思います。それを、「ダメな親だ!」と攻めるのは、僕はちょっと違うかな?と思います。声掛けの仕方や、対応策という本を僕も結構に読みますが、そんな綺麗に上手くいくことは皆無です。緊急性が高い時に、時計を見れば、誰だって焦ります。それが、その子が行きたかった習い事なんかの時にはこんなことが起こります。
親が焦ってしまう一つの事例
「もう時間がないよ。じゃあ、今日はお休みする、ピアノ?」すると、子供は「嫌だ!絶対に行く!」と泣き叫びます。「だったら、準備をしよう?」と伝えると「だって、この洋服じゃ嫌だ!自分で決めたお姫様のお洋服がいいのー!」と寝そべって訴えます。「でも、それじゃないと、習い事の先生に笑われちゃうから。もう、行かなきゃ間に合わないのよ…もうっ!いい加減にして!」
そんな時に、時計を見れば、誰だって、少し声を荒げて、「もう、行かない。もう、無理だから!そんなことばっか言って!自分のせいだからね!」と(脅しのような発言を)言ってしまいます。
ここで、忍耐を持って、常に笑顔で入れるかというのは、凄く難しいことだと思うのです。
話を戻します。
そして、僕は「なぜ叱ったのか」をBさんに、その本当の理由を伝えました。
友達が体調が悪い時には、自分のことだけでなく、相手のことも考えて助け合うこと。
これは、僕自身が息子に伝えたいと願うことでもあります。
「君が大切で、君が大好きだよ」
最後にそう伝えた時、Bさんの顔に少しだけ笑顔が戻ったのを今でも覚えています。
「叱る」のがすべて悪いわけではない
2年前の僕は、叱った後に必ず「自分の選択は正しかったのか?」と自分を責めていました。
でも、今なら自信を持って言えます。
「あの日の叱り方は、間違っていなかった」
叱ったことではなく、「叱り方」です。
大切なのは、叱ってしまった行為そのものではなく、「どう叱ったか」と「その後のフォロー」です。
なぜ叱ったのか、その理由を伝えること。
そして何よりも、「あなたという存在が大切だ」という揺るがない愛を伝えること。
プライドを捨ててでも、子供に謝罪すること。
それは、子供に「自分は大切な人間だ」と教えることでもあります。
もし今、あなたが自分を責めているなら、どうか思い出してください。
あなたの心の中にある葛藤は、あなたが子供のことを心から大切に思っている証拠です。
そして、そこに迷うなら自問自答してください。
「叱ったのは、子ども愛しているからなのか。それとも、自分が焦っていたのか」と…
叱った理由をもう一度、見つめ直してください。
そして、「叱る」という行為は、その苦しみを伴うからこそ、子供の心に深く響く愛の形になるのだと、
2年後の僕は信じています。
けして、安易に「叱ってもOKです」と言いたいわけではありません。
もちろん、基本として、「叱る」必要がない時に、叱る必要もありませんし、
叱らなくて済むなら、それを選択すべきです。
叱ってしまうことは、愛情があるからで、その後のフォローや自己反省、自己改善があり、叱らない方法を模索して、叱った理由や、叱ったことへの謝罪があるなら、子供を動かす「きっかけ」にもなるのです。
逆にそれらをせずに、叱ったり、怒ったりしているのは、それは単なる感情的になっていたということです。
感情的なのが悪いとも思いませんが、せめて、反省をして、次にいかす方が望ましいです。
それが出来るなら、あまり保護者さんには自分を攻めないで欲しいと願います。
あなたのその悩みは、きっと他の誰かの心を救う力になります。
もちろん、このことは、障害の重さによって変わることでもあります。
「理解力」という点で、そのあたりの対応の仕方は異なります。絶対に、叱らない方が良い子もいます。
だから、それらは、すべてがそこに集約するわけではありません。
最後に…Bさんのその後は
そして、最後になりますが、Bさんのその後をお伝えします。
それが、僕は「自分を正しかったかな?」と思えた理由になります。
「先生、先生は、あの時、私に真剣に叱ってくれたよね。最近、やっとわかったよ。あの時は私が悪かったの。あんな風に言ってくれたのは、先生だけだったよ。学校の先生は、本気で注意してくれないから」
学校の先生が向き合っていない?そういうわけではないとは思いますが、彼女が心を開いて考えてくれたように思えた瞬間でした。そして、彼女は、友達が病気の時は、友達に優しくしてくれて、病気の子の対応をしている先生に協力してくれるようになっていました。
「その子だから、そうなった」
そうなのかもしれませんが、
僕の対応の仕方は間違っていたのかもしれませんが、
彼女が変わってくれたことで、 僕はあの日のジレンマに、一つの答えを見つけられたのです。