※このブログは一番下にラジオ配信をつけています。blogを読むのが面倒な方は、ラジオを聞いて頂ければ、このブログの内容を理解していただけると思います。
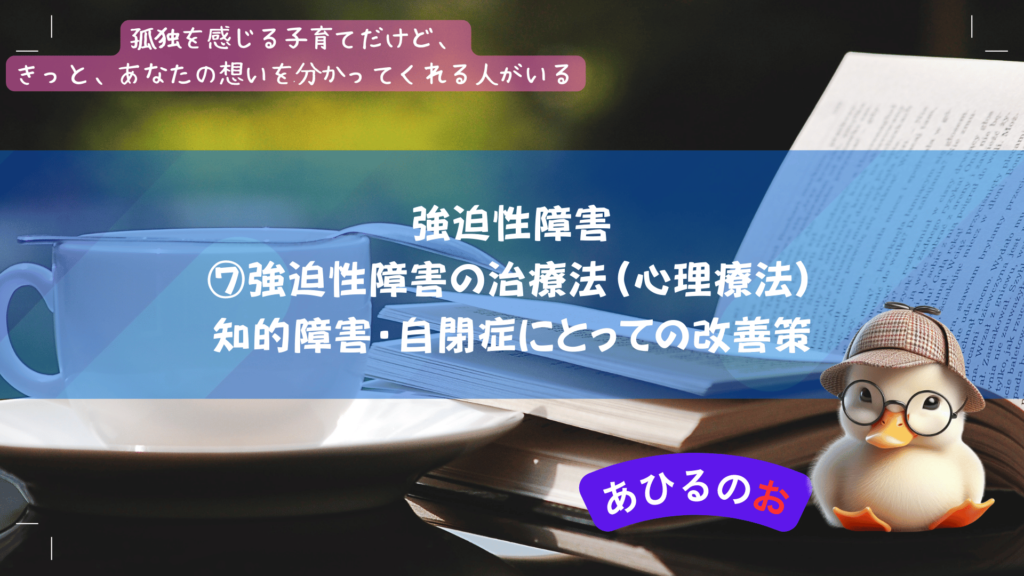
強迫性障害(OCD)の治療法:心理療法とは?
強迫性障害(OCD)の治療には、薬物療法と心理療法の2つのアプローチがあります。前回は、薬物療法について、うちの事例を含めて解説しました。なかでも、心理療法は根本的な改善を目指せる治療法として注目されています。今回は、OCD治療に効果的な**認知行動療法(CBT)や曝露反応妨害法(ERP)について、初心者でもわかりやすく解説します。
1. 認知行動療法(CBT)の基本とは?
認知行動療法(CBT)とは?
認知行動療法:CBT(Cognitive Behavioral Therapy)は、考え方(認知)と行動を変えることで、強迫観念や強迫行為を減らす治療法です。
OCDにおけるCBTの考え方
OCDでは、「手を洗わないと病気になるかもしれない」「確認しないと事故が起こるかも」といった強迫観念(不安を引き起こす考え)が生じ、その不安を和らげるために強迫行為(手洗いや確認を繰り返す行動)をしてしまいます。CBTでは、この強迫観念と強迫行為の悪循環を断ち切ることを目指します。
CBTの具体的なステップ
- 認知の歪みを理解する
- 「手を洗わないと大変なことになる」といった極端な考えが本当に正しいのかを検討します。
- 不安をコントロールする
- 不安が生じたときに、深呼吸やリラクゼーション法を活用して乗り越える練習をします。
- 行動を変える
- 実際に、強迫行為を減らすチャレンジを行い、不安が自然と消えていくことを体験します。
CBTの中でも、特にOCDに有効とされるのが曝露反応妨害法(ERP)です。
重要な「認知の歪み」については、下記で解説しています。↓
ペアレントトレーニング 第5回 ⑤自己肯定感の低下についてより深く考える | あひるのお 発達障害児パパママ blog 陽の日日記
上記リンク先のYouTube動画だと、15分40秒くらいから解説してます。
2. 曝露反応妨害法(ERP)の詳細と実施方法
曝露反応妨害法(ERP)とは?
ERP(Exposure and Response Prevention)は、OCDの治療において最も効果があるとされる行動療法です。ERPの基本的な考え方は、「あえて不安を引き起こす状況に身を置き、その後の強迫行為をやめることで、不安が自然と消えていくことを学ぶ」というものです。
ERPの実施方法
- 不安階層リストを作成する
- 例:「ドアノブを触る」→「トイレのドアノブを触る」→「手を洗わずに過ごす」
- 軽い不安から順番に挑戦していく。
- 不安を引き起こす行動(曝露)を行う
- 例:汚染恐怖の場合、ドアノブを意識的に触る。
- 重要:強迫行為(手洗いや消毒など)はせずに、そのまま耐える。
- 不安が自然と消えるのを待つ(反応妨害)
- 最初は強い不安を感じるが、時間が経つと不安は徐々に軽減していく。
- これを繰り返すことで、「不安は時間とともに消える」ことを学ぶ。
ERPの成功ポイント
- 最初から難しい課題に挑戦せず、徐々にステップアップする。
- 「不安を感じることは悪いことではない」と意識を変える。
- 医師・セラピストの指導のもとで行うのがベスト。
ERPを続けることで、強迫観念があっても強迫行為をせずに済むようになり、OCDの症状が大幅に改善されることが期待できます。
3. カウンセリングの効果
カウンセリングとは?
CBTやERPと組み合わせて、専門家との対話を通じてストレスを軽減し、対処法を学ぶのがカウンセリングの目的です。
カウンセリングの主な効果
- 不安の軽減
- 自分の気持ちを話すことで、心の整理ができる。
- OCDに対する理解が深まる
- OCDの仕組みを知り、適切な対処法を学ぶ。
- ストレス管理能力の向上
- セルフケアの方法(リラクゼーションやマインドフルネス)を身につける。
カウンセリングを受ける方法
- 精神科や心療内科での専門的カウンセリング
- オンラインカウンセリング(近年は自宅でも受けられる)
- 認知行動療法に精通した臨床心理士とのセッション
4.息子の強迫性障害のことで医師に言われたこと
「認知行動療法、主に曝露反応妨害法を利用するのは難しい」と言われました。その理由は、「特に暴露反応妨害法については、根本的に、恐怖・不安に打ち勝つ・慣れる必要があるが、間違ってしまうとそれを助長してしまったり、より深い不安にしてしまうことがある」ということでした。この点については、知的障害児には難易度が高いように、自分も思います。不安を助長してしまうことで、より症状がひどくなってしまうこともあり得るからです。
うちの息子は、小学校5年生・6年生が一番強迫性障害が酷く、その時には「喉に何か刺さった?」と気にするようになり、更には、「指さし行為を家族がするだけでパニックになる」ようになり、更に「車の中にいて窓がしまっていても、遠くでつばを吐いた人がいると、口の中に何か入った?」と聞くようにまでなりました。
これほどに、不安が強い子に、更に「不安に慣れろ」というのは酷な話のように思います。
実際に、うちが行っているのは、「合理的配慮」によって、「不安の軽減を図る」方を選択しています。不安や過度なストレスが掛からないように、最善の努力をしているつもりです。それが、他人には「わがままにしているね」と映る時があるかもしれませんが、上述のような過去を思い出すとそうせざるを得ないのも本音です。周りの視線もきになりますが、正直、コロナ禍でマスクをしながら唾液が口元にたれ、Tシャツがびっちょりになる息子を思い出せば、これ以上に不安にさせるという選択肢は選べないのです。
また、「暴露反応妨害法などを安易にするべきではない」と医師からアドバイスがありました。知的障害があってもなくても、そういった方法を専門家の知識なく行えば、逆効果になるという点もしっかり押さえてほしいと思います。
5. 知的障害がある場合のCBTやERPの適用について
知的障害がある場合、CBTやERPの実施は困難である場合が多いため、慎重に適用する必要があります。
適用が難しい理由
- 認知能力の問題
- CBTでは「認知の歪みを理解し、考え方を変える」ことが必要ですが、知的障害があると抽象的な思考や自己分析が難しいことがあります。
- ERPの負担が大きい
- ERPは強い不安を感じる場面に耐える必要がありますが、知的障害があると適切な自己調整が難しく、パニックや過度のストレスにつながる可能性があります。
- 意思疎通の問題
- 患者が自分の不安や考えを適切に伝えることが難しいと、治療がスムーズに進まないことがある。
知的障害がある場合の対応策
- CBTを簡略化する
- イラストや具体的な事例を用いて、視覚的に理解できるよう工夫する。
- 口頭だけでなく、実際の行動を交えて学習する。
- ERPの強度を調整する
- 初期段階では、不安を引き起こす状況を軽減し、徐々に慣らしていく。
- セラピストや家族のサポートのもとで、安全に行う。
- 他の療法と組み合わせる
- 行動療法だけでなく、音楽療法や感覚統合療法を併用して、ストレスを軽減する方法を取り入れる。
6. まとめ:心理療法でOCDを克服しよう!
- 認知行動療法(CBT)で強迫観念と強迫行為の関係を見直す。
- 曝露反応妨害法(ERP)で「不安は時間とともに消える」ことを体験する。
- カウンセリングでストレス管理を学び、心理的なサポートを受ける。
- 知的障害がある場合は、CBTやERPの適用を慎重に検討し、必要に応じて簡略化や代替療法を活用する。
心理療法は、薬に頼らずにOCDを根本から改善できる強力な治療法です!
OCDの症状に悩んでいる方は、専門家と一緒に取り組むことで、少しずつ改善が期待できます。まずは、心療内科や精神科の受診、またはオンラインカウンセリングなどを利用して、治療を始めてみましょう。しっかりとした医師のもとで行うのが一番良いと考えています。安易に自分でやってみよう!と保護者さんが考えるのはリスクを伴うと思います。
stand.fm(ラジオ配信)
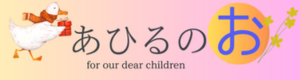
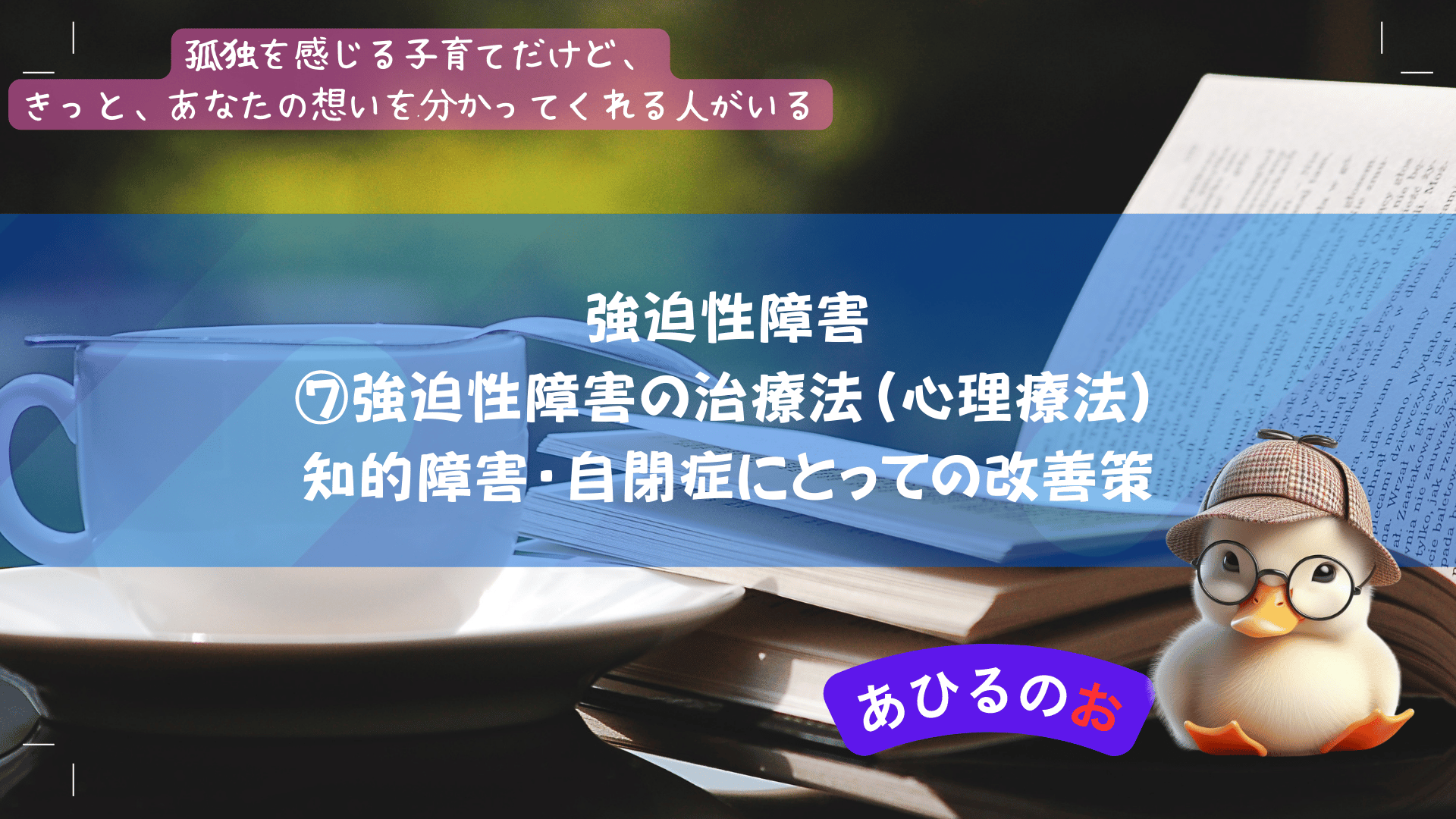
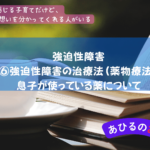
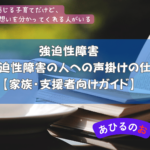
コメント