
ここでは、合理的配慮について考えていきたいと思います。初心者ママ向けに簡単に説明しています。
2024年4月1日より、改正された「障害者差別解消法」が施行され、民間事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が法的義務となりました 。これにより、これまで努力義務とされていた対応が、法的な責任として求められるようになっています。教育における「合理的配慮」について記事にしていきたいと思います。
✅この記事でわかること

最近では、「合理的配慮」という言葉が多く出てきました。親としては、子供の訴えの通りにすることで、「甘え」のように感じることもあり、悩ましい所ではないでしょうか。合理的配慮をどう考えるべきかを、初心者でもわかるように解説していきます。
- 合理的配慮とはなにか
- 発達障害の子どもに必要なサポートの具体例
- 学校・家庭でできる配慮のポイント
- 保護者が知っておきたい制度と相談先
はじめに|「合理的配慮」って聞いたことありますか?
「合理的配慮」という言葉、最近よく耳にしませんか?
これは発達障害などの障害のある人が、不利にならないように環境ややり方を工夫する「あたりまえのサポート」のことです。
「みんなと同じじゃなくていい。
自分のペースでゆっくり歩いていこう。前に一緒に歩いていくことが大切なんだよ」
合理的配慮とは?
文部科学省の「合理的配慮」とは?
難しく言えば…
「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と定義した。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。
※文部科学省「3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」より引用
文部科学省の「合理的配慮」を分かりやすく言えば
ということです。これをもっと分かりやすくお話をするならば、

「合理的配慮」とは、障害のある子どもがほかの子と同じように学校で学べるように、学校側が無理のない範囲で、その子に合わせたサポートや工夫をすることです。これをしないことは差別にあたると国際的にも決められています。
僕が考えた時に凄いなと思うことは、この文章の「これをしないことは差別にあたる」と決められている所です。同じスタートラインで、教育を気持ちよくうける権利は誰にも等しく与えられていることを感じます。等しく与えらえている権利だからこそ、「これをしないことは差別にあたる」のですから、合理的配慮というのは常に行われるべきこととなります。でも、実際には、そこに到達しているかと言えば、まだまだこれから。でも、こういった形で政府が考えてくれていることには、勇気を貰えますね。
※さらに文部科学省の「合理的配慮」についての解説はこちら
✅POINT
- 「特別扱い」ではなく「必要な工夫」
- 子どもが本来の力を発揮するための“手助け”
🏫学校での合理的配慮の具体例

| No. | 配慮の内容 | 対象となる困りごと |
|---|---|---|
| 1 | 指示は一度に1つずつ・視覚的に提示 | 言葉だけでは理解が難しく、混乱する |
| 2 | スケジュールや時間割を「見える化」 | 先の予定が読めないことで不安になる |
| 3 | 静かな場所で休憩できる「クールダウンスペース」を設ける | 感覚過敏・ストレスが強くなったときの対応 |
| 4 | 集団活動では「見学のみ」や「個別対応」を認める | 強い不安・パニックを起こすことがある |
| 5 | テストの時間延長・別室受験の許可 | プレッシャーに弱く、集中しにくい |
| 6 | 自席以外での学習(廊下・別室など)を柔軟に対応 | 音・視覚刺激への過敏さ |
| 7 | 感情が高ぶったときに使用する「合図カード」や「SOSカード」 | 言葉で助けを求めるのが難しい |
| 8 | ネガティブな言葉かけを避け、肯定的な声かけを意識する | 自己肯定感が低く、傷つきやすい |
| 9 | 人前での発表や発言は強制しない(別の方法で評価) | 緊張や対人不安が強い |
| 10 | 登校時間の調整や短時間登校からのステップアップ | 不安障害・うつ傾向での通学困難に対応 |
🏠家庭でできる配慮・サポート
家庭でも、合理的配慮の考え方を取り入れることは大切です。
🏠家庭での配慮(療育方法)例
- スケジュールを見える化
- 「絵カード」を作って視覚的に伝える
- 失敗しても叱らず、できたことを褒める
- 精神的な苦痛があるような時には、どうすれば落ち着けるのかを考える
保護者が知っておきたい制度(子ども家庭庁)
文部科学省
3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備
内閣府
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
📝まとめ|合理的配慮は「ちょっとした思いやり」
合理的配慮は、特別な支援ではなく「子どもの力を活かすための配慮・気配り・思いやりです。
どういった配慮をすれば、「その子がよりよく成長するのか」また、「その成長に対してよりよいサポートが出来るのか」を考えた工夫と言えるでしょう。
発達障害のある子どもたちがのびのびと生活できるように、まずは「どんなことに困っているか」を知ることから始めましょう。
そういった思いやりの心が、お子様の支えになって、難しい子育てにも絶えず愛情をもって継続できることに繋がるのだと思います。
次に読みたい記事
【体験談】うちの子が学校で受けた合理的配慮とは?
💬コメント欄へ
コメント欄は、このブログの一番下にあります。何かご意見があったら、是非、交流しましょう♪
💡「うちの子はこんな配慮をしてもらっていました」
💬「うちはこういうのが役立ちました」など、気軽にコメント頂けたら嬉しいです。
「PR」
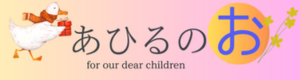

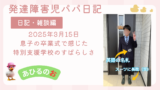
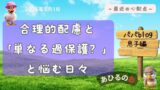
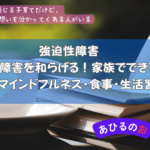

コメント