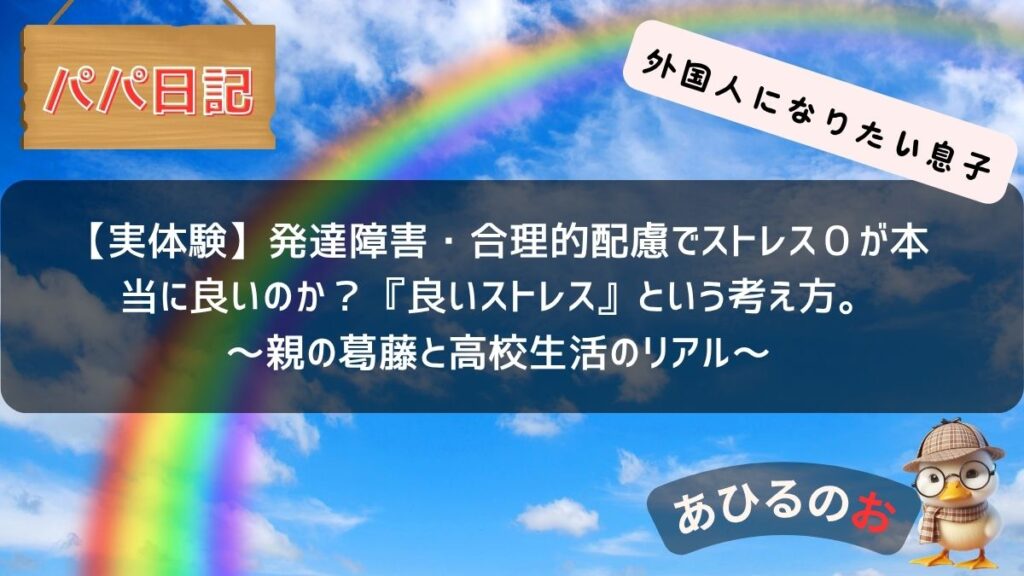
あなたのお子さんは「普通」に馴染めていますか?発達障害・強迫性障害を持つ息子の高校生活と、親が見つけた『良いストレス』という成長の鍵。
「我が子には、何の苦労もなく幸せになってほしい」――そう願う親心は当然です。しかし、発達障害(自閉症・強迫性障害)を持つ息子が高校に進学し、合理的配慮を求める中で、私はある疑問に直面しました。「何でも子どもの言う通りで本当に良いのか?」と。一見“過保護”に見える配慮が、かえって子どもの自己肯定感や社会適応能力を奪う可能性もあるのではないでしょうか?
このブログでは、息子が直面した具体的な困難と、中学校・高校での配慮の違い、そして私たち親が悩み抜いてたどり着いた**「良いストレス」という新たな視点をお話しします。お子さんの将来の幸福**を真剣に考える保護者の皆さん、ぜひ一緒に「本当に必要な合理的配慮」について考えてみませんか?

今日の日記では、1学期を振り返りたいと思います。これは、実は6月に書いていた日記なんです。途中で、かけずに放置していました。それを少し手直ししています。皆さんが、「合理的配慮」について考えて貰うきっかけになって貰えればと思います。
「新学期」からの学校生活と変化
息子のことについて言うと、中学校を卒業して、高等学校の方に移りました。 やっと1学期が終わり、落ち着いた生活が出来るかと思いきや、実は、うちの家族は不安定そのものです(笑)色々書くと分かりづらいので、息子のことに焦点を当てて考えていきたいと思います。
当然一学期は、息子は環境に慣れることができなくて、戸惑ったりとかしています(涙)
新学期、新学年を迎え、みんさんのお子様も、心配もあり、現実的にそうやって難しい部分が出てきてしまったり、また逆に上手くいき、ほっとしているというようなこともあると思います。
実際、うちの子供に関しては高等学校に上がって、
親の中でも葛藤があって、変化に息子の方がついていけず学校の方に休んだりとか行ったりとかしている状況でした。
子供の高校生活の難しさ 強迫性障害の具体的な息子の困難事例
今はまさに、「バランスのすごく難しい時期に入っているな」というような状況です。
それでちょっと息子のことを中心に話しますが、中等部から高等部の方に変わり、今は、いろんな葛藤があるんです。
息子は、もともと鬼滅の刃が苦手で、それから繋がって「鬼」が苦手になり、鬼というのは日本の話によく出てくるということで、結果的に…「海外のキャラクターだったら安心!」という形になったんですね。 息子はわかってないんですけど、セガのソニックっていうキャラクターを それも海外だと思ってしまっていて、ソニックが好きになったのです。
もともとはペガサスが好きで、また、ココメロンというマレーシアで作られているYouTubeのキャラクターが好きになり、それのグッズを集め、そこから波及して、その頃から少しずつ海外キャラクターということを言い始めていました。
いろんな海外キャラクターを見ているんですけれども、ちょうどその頃にネットフリックスをうちの方で入れたので、ネットフリックスで海外系のもののキャラクターを探し当て、
「海外のキャラクターなら安心。だから、好き」
という風になっていました。
そこから、「僕は英語が良い、漢字嫌い。日本人嫌い。外国人になるんだ」と言い始めました。
中等部の頃は結構にそれを認めてもらえていて、うちの息子は、
「僕のことを ミスター〇〇〇 と呼んでください」と学校の校内放送で訴えたほどでした(汗)
英語のように苗字と名前を反対にして呼ばれないと納得できないという感じです。名前で言うと大谷翔平さんって有名ですけど、大谷翔平で言うと「ミスター翔平大谷」って名前を逆に呼ぶみたいな、「そう呼んでください」みたいなことを言ったら学校中の先生が合理的配慮なのか、そういう風に呼んでくれたのでした。
当然に、息子はそう呼ばれるたびに喜んでいたのですが、ところがですね、すごく厄介なのが、そういう感じに呼んでくれないことに対する不満というかが起こっちゃうんです。例えば、普通に、「大谷翔平さん」みたいに呼ばれると不満に感じて、不機嫌になっちゃうわけです。
それだけでとどまらず、なんかちょっと強制的という感じで、「友達にもそう呼んでください」となり、 呼ばないと「なんなん!ひどい!」みたいな気持ちになっちゃう。
そのネガティブなところがどんどん膨らんで、もっと悪いネガティブなことを引き付けてきちゃうっていう子なので…難しいですね(苦笑)
これは、強迫性障害でいう巻き込みみたいなもので、周りの人間を巻き込んで不快な気持ちを与えてしまうわけです。「僕が呼んでほしい呼び方で呼ばないなんて酷い。もう学校は嫌だ」みたいな感じになり、不快であることを訴えてしまうわけです。
※強迫性障害の詳細はこちらの記事でも解説しています。自閉症傾向のあるお子さんは、強迫性障害でなくても参考になると思います。
中学校生活から高等学校への変化 知的障害が故の苦悩
それで中等部の頃には、『学校に来る』ということが息子の第一目標で、そういった配慮が結構されていていました。3年間同じ先生が見てくれたんですが、本当に思いやりのある方で、とにかくうちの息子は「学校に来てください」というような形で、多少の無茶も飲み込んでくれて、配慮を持ってくれてたんですね。
ところが、高等部になり、そういった配慮という部分にちょっとメスが入るというか、それはできないよということが結構多くなってきたわけです。
でも、実はうちの子ってすごく理解ができそうで、実は結構の割合で理解ができないんです。
例えば、理屈をきちんと説明して「それはダメですよ」と伝えたとしても、
息子の心の中に何が残るかというと、理屈は全く残ってなくて、
「この人は分かってくれなかった」というのだけが残っちゃうんです。
例えば、卒業式の時に、ミスター○○○なんて、卒業証書をもらう前に先生は息子を呼べません。 ところが、それを言えないことをどうにかしようということで、卒業式の時には名札をぶら下げたんです。
その手のひらサイズの名札の中に【僕のことをミスター○○○と呼んでください】と書いてある。 それで息子の方は安心して不満な卒業式に出れました。 でも、やっぱりです、不満は残ったんです。 「卒業式は嫌だったね。僕は外国人になりたいのに、名前を呼んでくれない」といつまでも言うんです。「英語で呼んでくれなかったじゃないか」と(苦笑)
高等部に入ってからも同じようなことが続きます。先生が同じように、理屈を踏まえて、「すべてを求めているように呼ぶことは出来ないよ」言った時に、そのと時には、息子は「うんうんうん」って聞けるんです。が! 心の中に残るのは、「先生は、僕がそういうふうに呼んで欲しいのに理解をしてくれなかった」っていう部分だけが残っちゃうんです。
合理的配慮とストレスの関係(将来の幸福をどうつかむか?)

ここからが今日の日記の本題です。みなさんだったらどう考えますか?同じような事例があったら教えてほしいです。コメント欄でやり取りが出来たら嬉しいです。
うちの子の場合は自閉症が強かったりとか、あとは中等度の知的障害があるので、たぶん丁寧に分かりやすい言葉で理解をしてもらうために説明しても、直感的な「嫌!」が勝ってしまいます。理解もしきれず、「反対された!」とか「僕のことを理解してくれなかった!」だけが強く残ってしまって、先生に対しての嫌悪感にまでつながってしまうのです。
■高等部における強迫性障害とストレスへの対応
高等部になり、中等部のころとの対応の仕方の違いに、息子は戸惑い、不満を抱いています。
対応をどう変えたのか?というと、
単純に常識的なことを曲げない。少し嫌悪感を感じても丁寧に説明する。ダメなものはダメだと説明して、淡々としている。ただし、叱ったりはしない。本当に小さなストレスで、息子の状況を見つめていく。耐える力を伸ばす。
中等部までは、本当に、些細なことでも息子の希望に合わせてきました。そうでないと、凄い癇癪でしたし、小学校の頃の息子に戻したくない一心でした。
それによって、強迫性障害の確認行動もめちゃ増えました。 「ストレスがかかっているな」という状態ですので、我慢が必要です。ただ、この我慢というのは、親も一緒です。息子のために、少し親も我慢が必要になるのです。常に、親としてどうしていこうかと悩ましい葛藤が続きます。
※小学生の頃の息子(強迫性障害発症)から中学生の頃の息子
小学生の頃の息子
息子の症状は、小学校時代に特に強く現れ、親として見ているのが辛いほどでした。例えば、「唾を飲み込んではいけない」という強迫観念から、口の中に唾を溜めてしまい、話すときにTシャツの首元がびしょ濡れになることもありました。コロナ禍でマスクをしていたため、本人は周りに気づかれていないと思っていましたが、周囲から見るとその状態は明らかで、心が痛みました。また、唾が気になるあまり、舌をかきむしって血が出たり、腫れてしまったりすることもありました。そんな姿を見るたびに、「どうにかしてあげたい」と思う一方で、どうサポートすべきか悩む日々でした。
中学生の頃の息子
中学校に進学した際、息子の状態を学校に伝え、「以前の状態に戻させたくない」とお願いしました。具体的に、合理的配慮をお願いしました。息子は非常に繊細で、些細なことにも過剰に反応し、落ち込んだり苛立ったりして精神的なコントロールが難しくなることがあります。その結果、学校に行けなくなることもありました。
合理的配慮の考え方とその難しさ
合理的配慮とは、文部科学省によると、「障害のある子どもが他の子どもと平等に教育を受ける権利を確保するために、必要かつ適切な変更や調整を行うこと」と定義されています。ただし、これは子どもの要求をすべて受け入れることではなく、過度な負担にならない範囲での配慮を指します。例えば、以下のような例が挙げられています:
- バリアフリー設備や適切な学習スペースの確保
- 個別指導やデジタル教材の活用
- クールダウン用の小部屋の提供
- 視覚的な情報提示や対人関係への配慮
息子の場合は、例えば「英語で名前を呼んでほしい」という要望がありました。これは文部科学省の例には直接当てはまりませんが、「呼ばれ方」がきっかけで強いストレスを感じ、授業や食事がままならなくなるため、中学校ではこの配慮を取り入れてもらいました。
合理的配慮によるノンストレスの状態が本当に良いのか?の親の葛藤
しかし、高校生になった今、息子の将来を考えたとき、「どこまで配慮すべきか」という葛藤が生じています。
上述の通り、例えば、英語で名前を呼ばないと不快になり、ネガティブな感情が連鎖してしまいます。学校に配慮をお願いすれば、息子は一時的に安心するかもしれませんが、『これが長期的に彼の幸せにつながるのか』と疑問が残ります。
―私は、息子に「本当の幸せ」を手に入れてほしいと願っています。
本当の幸せとは、例えば大谷翔平選手が努力の末にホームランを打つような、努力と成果による喜びだと考えています。社会生活では、誰しも小さなストレスを乗り越える必要があります。体がだるい日でも仕事を頑張る——こうした小さな我慢が、実は自己成長や幸せにつながるのです。
息子にこの小さなストレスを全く与えず、すべての要求に応えることが、果たして彼の将来にプラスになるのか。将来の幸福につながるのか。「過保護(合理的配慮を入れすぎている状態)にすることで、息子の将来の自己肯定感や社会での適応力を奪ってしまうのではないか」という葛藤が常に僕の頭の中にはあるのです。この葛藤こそが、合理的配慮を考える上で大きな課題です。
他の生徒の事例:発達障害(支援級クラスの子に対して)思う事
例えば、宿題を嫌がる子どもがいたとします。「宿題をすると暴れてしまうから」と宿題を免除することが合理的配慮になるかもしれません。しかし、「中学校を卒業する頃、精神が落ち着いてきた時、学力が全くなく、自己肯定感が下がってしまうのだとしたら?」そんなことを考えることがあります。
ある程度の努力を積み重ね、漢字や算数の基礎を身につけていたら、それが自信につながるかもしれないのに——そんな思いが頭をよぎります。発達障害でも軽く、大人になった時には福祉のお世話にならずに、就職して生きていくのなら…高校に普通に入るかもしれない。せっかく精神的に落ち着いた時には、学力が必要になるかもしれない。そんな葛藤もあるでしょう。僕ら親は、そういった葛藤の繰り返しではないでしょうか?
※合理的配慮についてもっと知りたい方はこちらでも分かりやすく解説しています↓
文部科学省の「合理的配慮」についてのページはこちら↓
3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備:文部科学省
合理的配慮と「良いストレス」の関係性

本当にストレスって悪いものかな?

ストレスってつらいじゃん!

でもね、ストレスでも、「良いストレス」ってものもあるんだよ
僕が考える良いストレスとは…
新しい挑戦や目標に向かう際に感じる適度なプレッシャーは、「良いストレス」。自己成長に不可欠。例えば、仕事でのプレゼンテーションやスポーツの試合前の緊張感は、集中力を高め、普段以上の力を引き出すことがあります。この「良いストレス」は、僕たちが困難を乗り越え、適応力を養うための原動力となるのだと思います。そして、それが生む達成感。それが、人の幸福にとって、凄く重要だと思うのです。過度なストレスは心身に悪影響を及ぼしますが、適切な「良いストレス」は、私たちの幸福感を引き出すきっかけになります
息子に願うこと
作業所や社会に出る段階で、息子が少しでも強い自分になれるよう願っています。
ほんの少しのストレスを乗り越える力を育てたい。
でも、配慮を減らすと生活がままならなくなり、悪循環に陥るリスクもある。
このバランスが、本当に難しいと考えます。
親としての悩みと願い学年や先生が変わるたびに、新しい環境に慣れるための試行錯誤が続きます。
5月や6月頃になると、子どもらしさが出てきて、学校に行きたくないと言い出し、緊張が解けて新たな課題が現れたりします。そして、夏休みを迎え、一時的な気持ちの楽さが芽生えても、2学期には別の問題が現れます(涙)
そんなとき、親として「これでいいのか」と自問自答します。
合理的配慮の答えは簡単には見つかりません。
どの親御さんも、同じように悩んでいるのではないでしょうか。
「学校に行きたくないと言われ、行かせない…でも、本当に良いのか?」とか。
でも、そのためにどの程度の配慮が必要か、どこまで小さなストレスを与えるべきか—
その線引きは、いつも悩ましいもの。
その答えは、僕にはまだ分かりません。ただ、毎日、模索して、伝えることを伝え続ける努力とその境界線をしっかり見極める日常を、親として常に向き合っていきたいと思います。皆さんのお子さんも、新しい環境に慣れ、充実した日々を送れるよう…願っています。
まとめ
今回は、今の悩みを打ち明けていきました。実際には、他にも色々な悩みがまだまだ混在している我が家です(笑)
ただ、今回のような悩みは、障害児の家族さんにとっては、本当に悩ましいものだと思っています。子供たちの本来の幸せを手に入れるために、すべて「子どもの言うがままで良いのかな」「不登校になったけれど、学校に行けというべきではないのかな」そういった悩みは、今回、提示している我が家の悩みと似ているものだと思います。是非、一度、お子様の本当の意味での「幸せ」を見つめ直すきっかけになればと思います。何かあれば、是非、コメントを頂けたら幸いです。一緒に頑張っていきましょう。読んで頂いてありがとうございました。
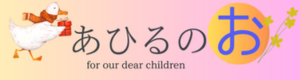
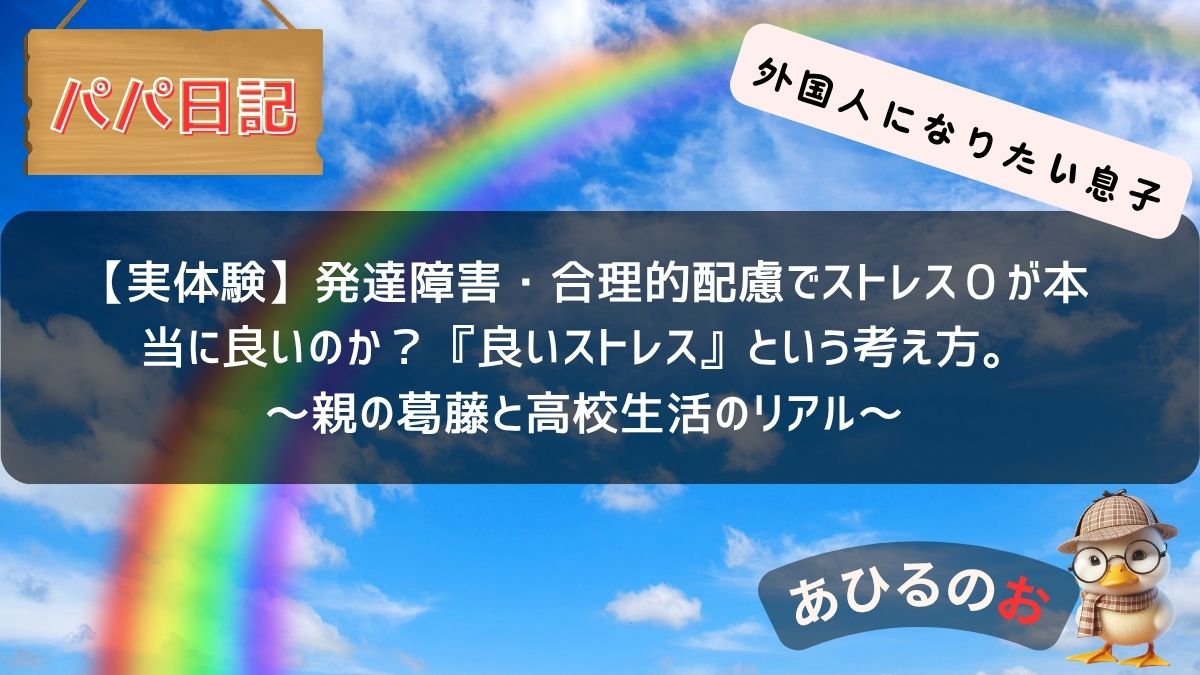
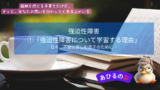




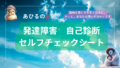
-120x68.jpg)





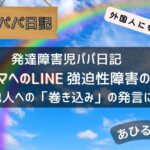
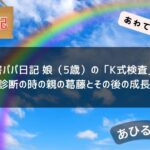
コメント