以下は、文部科学省の「合理的配慮」について、初心者にもわかりやすく要約した内容になります。なぜ、理解が必要なのか?

文部科学省の見識を理解することで、子供の悩ましい所を先生に相談する際に、「合理的配慮を持ってもらう」ことの気持ちの負担が楽になります。お子さんが学校でどのようなサポートを受けられるのか、その根拠となる考え方を知ることで、学校との対話がスムーズになります。「合理的配慮」という共通の言葉で、お子さんのニーズや必要な支援について具体的に話し合うことができるようになります。
3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備
※文部科学省「3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」より引用
↑これを要約していきます。

文部科学省の学校の「合理的配慮」を理解した際のメリット
合理的配慮について理解を深めることは、障害のあるお子さんを持つ保護者の方にとって、たくさんのメリットがあります。
まず、お子さんが学校でどのようなサポートを受けられるのか、その根拠となる考え方を知ることで、学校との対話がスムーズになります。「合理的配慮」という共通の言葉で、お子さんのニーズや必要な支援について具体的に話し合うことができるようになります。
また、どのようなサポートが「合理的配慮」として求められるのか、その範囲や考え方を知ることで、保護者として学校に何を求めて良いのかが明確になります。遠慮したり、諦めてしまったりすることなく、お子さんの権利として必要なサポートを主張しやすくなります。
さらに、学校側の説明や提案が、合理的配慮の考え方に沿っているかどうかを判断できるようになるため、より適切で質の高い支援がお子さんに提供される可能性が高まります。もし、疑問や納得できない点があれば、自信を持って質問したり、意見を述べたりすることができるでしょう。
そして、合理的配慮は個別性が高いものだと理解することで、お子さん一人ひとりのニーズに合った、きめ細やかなサポートを学校と一緒に考えていく視点を持つことができます。他の事例にとらわれず、「うちの子には何が必要か」という軸で考えることができるようになります。
最終的には、お子さんが学校生活をより安心して、意欲的に過ごせるようになることが、保護者にとって最大のメリットと言えるでしょう。
※ちなみに、我が家の合理的配慮については、
合理的配慮とは何か?(合理的配慮の定義)
「障害者の権利に関する条約」という、障害のある人の権利を守るための国際的な約束事について説明しています。特に「教育」と「合理的配慮」という点が重要です。
- 障害のある人も教育を受ける権利がある: この条約では、障害のある人も他の人と同じように教育を受ける権利があるとはっきり書かれています。
- インクルーシブ教育: そのために、「インクルーシブ教育システム」という、障害のある子もそうでない子も一緒に学ぶ教育の仕組みを作ることが大切だとされています。
- 合理的配慮は権利を実現するためのもの: そして、この教育を受ける権利を実現するために、一人ひとりに必要な「合理的配慮」を提供することが重要だとされています。
- 合理的配慮の定義: 「合理的配慮」とは、「障害のある人が他の人と平等に、色々な権利や自由を使えるようにするために必要な、適切で無理のない変更や調整」のことです。ここでいう「負担」は、サポートする側(学校など)にかかる負担のことです。
- 合理的配慮の否定は差別: この条約では、「合理的配慮を提供しないこと」も、障害を理由とする差別の一種だとされています。つまり、必要なサポートをしないことは、差別にあたるということです。
簡単に言うと、この条約は「障害のある人もみんなと一緒に教育を受ける権利があり、そのために、その子に必要なサポート(合理的配慮)をすることは当たり前のことで、もしそれをしないことは差別ですよ」と述べているのです。障害があることで教育の機会が奪われることがないよう、すべての子どもが学べる環境を整えることが求められているのです。
合理的配慮と基礎的環境整備の違い

- 国や自治体による環境整備(基礎的環境整備): 国や都道府県、市町村は、法律や予算に基づいて、障害のあるお子さんが学びやすいように、学校全体の環境を整える役割を担っています。これは、みんなが使えるように準備された、サポートの土台となるものです。例えば、スロープやエレベーター、特別な教材などがこれにあたります。この土台となる環境整備のことを、ここでは「基礎的環境整備」と呼んでいます。
- 学校ごとの個別サポート(合理的配慮): そして、それぞれの学校は、この「基礎的環境整備」をベースにして、さらに、一人ひとりのお子さんの状態や困っていることに合わせた特別なサポート(これが「合理的配慮」です)を提供します。
- 基礎的環境整備が大切: 国や自治体による「基礎的環境整備」がしっかりしていることは、学校が「合理的配慮」を提供する上でとても重要です。
- 合理的配慮は一人ひとり違うから、例で示す: 「合理的配慮」は、本当に色々な形があり、すべてを具体的に説明することは難しいです。そこで、この文章では、「教育の内容や方法」「サポート体制」「学校の施設や設備」という3つの観点から、「合理的配慮」の考え方を整理し、それぞれの障害の種類に応じて、よくあるサポートの例を示しています。ただし、これはあくまで例なので、この例以外にも、その子に必要なサポートはたくさんあるということです。
つまり、障害のあるお子さんへのサポートは、国や自治体が作る学びやすい土台があって、その上で、学校が一人ひとりの状態に合わせて、さらにきめ細やかなサポートをしていく、というイメージです。
合理的配慮の基本的な考え方
○ 「合理的配慮」を行う前提として、学校教育に求めるものを以下のとおり整理した。(※文部科学省 3.「障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」の 5「合理的配慮」の決定に当たっての基本的考え方を引用)
(ア)障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び共に育つ理念を共有する教育
(イ)一人一人の状態を把握し、一人一人の能力の最大限の伸長を図る教育(確かな学力の育成を含む)
(ウ)健康状態の維持・改善を図り、生涯にわたる健康の基盤をつくる教育
(エ)コミュニケーション及び人との関わりを広げる教育
(オ)自己理解を深め自立し社会参加することを目指した教育
(カ)自己肯定感を高めていく教育
○ これらは、障害者の権利に関する条約第24条第1項の目的である、
- (a)人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。
- (b)障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。
- (c)障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。
と方向性を同じくするものであり、「合理的配慮」の決定に当たっては、これらの目的に合致するかどうかの観点から検討が行われることが重要である。
合理的配慮はどのように決まっていくのか?
学校が障害のあるお子さんに対して行う「合理的配慮」という特別なサポートを、どのように決めて、どのように提供していくかについて説明しています。大切なポイントは以下の通りです。
- まずはお子さんのことをよく知る: 学校は、お子さんの興味や得意なこと、苦手なこと、健康状態などをしっかり把握することから始めます。
- みんなで話し合って決める: その上で、学校の先生だけでなく、お子さん本人や保護者の方も一緒に、どんなサポートが必要かを話し合います。お子さんの成長に合わせて、どんなサポートが良いかを考えることが大切です。
- 「個別の教育支援計画」に書く: 話し合って決まったサポートの内容は、「個別の教育支援計画」という、お子さん一人ひとりのための特別な計画書に書かれることが望ましいです。これは、お子さんの成長をサポートするための大切な設計図になります。
- 無理のない範囲でサポート: 学校は、先生の配置や経済的側面のことも考えながら、無理のない範囲でできるサポートを考えます。今、何が一番必要か、何を優先するかを、みんなで理解することが大切です。
- もし意見が違ったら: もし、学校と保護者の方の意見が合わない場合は、「教育支援委員会」(仮称)という専門家が集まる場所に相談して、解決策を探ることが望ましいです。
- 学校、家庭、地域みんなで協力: お子さんの成長には、学校だけでなく、家庭や地域社会の協力もとても大切です。学校で学ぶこと、家庭での親子の触れ合い、地域での友達との遊びなど、色々な経験を通して、お子さんは豊かに成長していきます。みんなで協力して、お子さんの成長を支えていきましょう。
つまり、「合理的配慮」は、学校がお子さんのことをよく理解し、保護者の方ともよく話し合って、お子さんに合ったサポートを一緒に考えていくもの。そして、お子さんの成長には、学校だけでなく、家庭や地域社会の温かい協力が不可欠だということです。
合理的配慮の今後の課題と取り組み
合理的配慮は比較的新しい考え方で、学校や保護者の間でもまだ理解が十分とは言えません。そのため、国として情報を集めたデータベースの整備や調査研究が必要とされており、教育現場での支援の質を高めるための取り組みが求められています。また、配慮の効果を評価し、改善を重ねていく「PDCAサイクル」の仕組みづくりも重要です。
【合理的配慮】教育内容・方法の工夫。お子さんの学びをサポートする大切な視点
合理的配慮の重要な柱の一つである「教育内容・方法」について、詳しく見ていきましょう。これは、お子さんがよりスムーズに、そして効果的に学習を進めていくために、学校がどのような点に配慮するのかを示したものです。
1-1. 教育内容:学びの土台を一人ひとりに合わせて
教育内容に関する配慮は、大きく分けて二つの視点があります。
学習上または生活上の困難を改善・克服するための配慮
「うちの子、勉強や学校生活でちょっと困っていることがあるみたい…」そんな時に大切なのが、この視点です。
- 主体的な改善・克服をサポート: 障害によって学習や生活で 困っているお子さんが、自分自身でその 困りごと 乗り越え、できることを増やしていけるように支援します。
- 個性と特性を伸ばす: お子さん一人ひとりの個性や、障害による特性を理解し、その持っている力を最大限に引き出せるようなサポートを行います。
- 必要な知識・技能・態度・習慣を育む: 将来、社会の中で自立していくために必要な知識やスキル、前向きな姿勢や良い習慣を身につけられるように、丁寧に教えます。
学習内容の変更・調整
「みんなと同じ内容で、うちの子も本当に大丈夫かな?」と感じることはありませんか?この視点は、お子さんの「学びやすさ」に焦点を当てています。
- 認知特性や体の動きに合わせた工夫: 物事の理解の仕方や、体の動かし方には個人差があります。お子さんの特性に合わせて、学習する内容の量や進め方、理解度を確認する方法などを調整します。
- 発達段階や年齢を考慮: お子さんの成長段階や年齢に合わせて、無理なく学習に取り組めるように内容を考えます。
- 卒業後の生活や進路を見据えて: 将来、どのような生活を送りたいか、どんな道に進みたいかというお子さんの希望を視野に入れながら、今学ぶべきことを大切にします。
- 人間関係や自己選択の機会を大切に: 学習を通して、周りの人と良い関係を築いたり、自分で考え、自分で決める経験を増やせるように配慮します。
1-2. 教育方法:学び方を工夫して、もっと分かりやすく
教育内容だけでなく、「どのように学ぶか」という方法も、お子さんの理解を深める上で非常に重要です。
情報・コミュニケーションと教材の配慮
「うちの子に情報がきちんと伝わっているかな?」「どんな教材なら分かりやすいかな?」そんな疑問に答えるのが、この視点です。
- 情報保障とコミュニケーション方法への配慮: 聞こえにくいお子さんには手話や文字で伝える、見えにくいお子さんには音声で伝えるなど、お子さんの状態に合わせた情報伝達の方法を考えます。コミュニケーションがスムーズになるような工夫も大切です。
- 教材の活用への配慮: ICT(情報通信技術)を活用した教材や、学習を助ける補助具など、お子さんにとって分かりやすく、使いやすい教材を選び、活用します。
学習機会や体験の確保
「病気で授業を休んでばかり…」「他の子と同じような経験ができていないかも…」そんな心配をサポートするのが、この視点です。
- 学習空白への対応: 治療などで学校を休んでしまった場合でも、遅れを取り戻せるように、個別の課題を出したり、オンラインで授業に参加できるようにするなど、学習機会を確保する方法を考えます。
- 経験不足への配慮: 障害によって経験が不足しがちなお子さんに対して、実際に触れたり、試したりする体験的な学習を積極的に取り入れ、理解を深めます。
- 入学試験やその他の試験での配慮: 試験を受ける際に、時間延長や別室での受験など、お子さんの状態に合わせた配慮を行います。
心理面・健康面の配慮
「学校で不安な気持ちになっていないかな?」「体調が悪くても無理していないかな?」お子さんの心の健康と体の健康は、学びの土台です。
- 分かりやすい情報提供と確認: 学習の予定や進め方を、お子さんに分かりやすい方法で事前に伝え、いつでも確認できるようにすることで、安心感を持って学習に取り組めるようにします。
- 良好な人間関係の構築: 集団の中でうまくコミュニケーションが取れるようにサポートし、周りの生徒が障害について理解を深められるような働きかけを行います。
- 心理的不安の軽減: 学習の見通しを持てるように、予定や進め方を分かりやすく伝えたり、周囲の状況を理解しやすくすることで、お子さんの不安な気持ちを取り除きます。
- 健康状態に合わせた柔軟な対応: 体調が優れない時には、学習内容や方法を無理のない範囲で調整します。
- 自己肯定感を高める: 障害からくる不安や孤独感を和らげ、お子さんが自分自身を肯定的に捉えられるようにサポートします。
はい、承知いたしました。引き続き、初心者の方にも分かりやすく、ブログ形式で「合理的配慮」の残りの二つの観点について解説しますね。
【合理的配慮】学びを支える「支援体制」と「施設・設備」の整備
お子さんの学校生活全体を支える「支援体制」と「施設・設備」という二つの重要な観点を見ていきましょう。
2. 支援体制:みんなで力を合わせるサポートネットワーク
合理的配慮は、一人の先生だけで実現できるものではありません。学校全体、そして学校の外の様々な専門家や機関との連携が不可欠です。
専門性のある指導体制の整備
「うちの子に必要な専門的なサポートは受けられるのかな?」そんな不安を感じている保護者の方もいるかもしれません。この視点は、学校がどのように専門的なサポート体制を整えているかを示しています。
- 校長のリーダーシップ: 学校のリーダーである校長先生が中心となり、学校全体で専門的な指導体制をしっかりと作り上げます。
- 役割分担と連携: 個別の教育支援計画や指導計画を作る中で、学校の内外の様々な関係者が、それぞれの役割を理解し、協力してサポートを行います。
- 適切な人的配置: 必要に応じて、支援員の方などのサポートスタッフを配置します。
- 外部の専門家の活用: 通級指導教室や特別支援学級、特別支援学校のセンター的機能、専門家チームからのアドバイスなど、学校の外の専門的な力を積極的に借ります。
- 関係機関との連携: 医療機関、保健所、福祉施設、労働関係機関など、様々な分野の専門機関と連携し、お子さんにとって必要なサポートを総合的に提供します。
幼児児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
「周りの子は、うちの子のことを理解してくれるかな?」「私も周りの保護者の方とどう関わればいいんだろう?」合理的配慮を進めるためには、周りの理解が不可欠です。
- 周りの子供たちの理解を深める: 障害のあるお子さんが、日常生活や学習でどのような 困りごとを抱えているのかを、周りの子供たちに分かりやすく伝えます。
- 共生の心を育む機会: 障害のあるお子さんとないお子さんが、一緒に活動する中で、お互いを尊重し、支え合う心を育む機会を作ります。障害のあるお子さん自身が、自分の障害について周りの人に伝える機会も大切にします。
- 保護者や地域への理解啓発: 保護者の方々や地域の方々に向けても、障害について理解を深めてもらうための活動を行います。
災害時等の支援体制の整備
「もし災害が起きたら、うちの子は安全に避難できるだろうか?」災害はいつ起こるか分かりません。万が一の時に備えた体制づくりが重要です。
- 災害時対応マニュアルの整備: 災害が起こった時の対応について、お子さんの状態を考慮し、危険の予測、避難方法、人員配置などを具体的に定めたマニュアルを作成します。
- 避難訓練での配慮: 避難訓練などを行う際も、お子さん一人ひとりの障害の状態に合わせて、安全に避難できるよう配慮します。
3. 施設・設備:誰もが安全に、そして学びやすい環境づくり
学校の建物や設備は、すべてのお子さんが快適に学校生活を送るための基盤です。
校内環境のバリアフリー化
「車いすでも移動しやすいかな?」「階段しかないけど大丈夫かな?」 環境面の不安 をなくすための取り組みです。
- バリアフリー化の計画: スロープ、手すり、使いやすいトイレ、広い出入り口、エレベーターなど、障害のあるお子さんが安全かつスムーズに移動できるよう、施設の整備計画を立てる際に配慮します。
- 既存施設の改善: 現在ある学校施設についても、障害のあるお子さんの在籍状況などを考慮しながら、計画的にバリアフリー化を進めます。
発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
「うちの子の特性に合った学習スペースはあるのかな?」「集中できる環境だといいな…」お子さんの学びを深めるための環境整備です。
- 教育機器等の導入: 必要に応じて、学習をサポートする様々な機器や設備を導入します。
- 教室等の工夫: 教室などの施設や設備について、分かりやすさ、使いやすさに配慮します。
- 環境要因への配慮: 日当たり、室温、騒音など、学習に影響を与える環境要因にも配慮します。
- 心のケアへの配慮: 心理的なサポートが必要なお子さんのために、安心して過ごせるスペースなどを整備します。
災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮
災害時においても、障害のあるお子さんが安全に過ごせるように、特別な配慮が必要です。
- 災害対策設備の整備: 災害時に必要となる設備(非常用電源、避難器具など)を、お子さんの状態に合わせて整備します。
まとめ
今回は、文部科学省の「合理的配慮」についてまとめてみました。分かりやすく解説したつもりですが、いかがだったでしょうか?
文部科学省が推進する「合理的配慮」の仕組みが分かってくると、「どのように相談をしていくべきか」が分かったり、そもそもの相談の時点で、「先生に迷惑では?」「こんなこと言っていいのかな?」と悩む保護者さんにとっては、少しは気が楽になったのではないかな?と思います。
大切なのは、「みんなで考えていこう」と周りを巻き込む力なんだな…とつくづく感じます。
もしも、保護者さんが、実生活の中で苦しいと子育てを一人で抱え込み、自分自身が疲れ切ってしまっているのなら、もしくはそうなる前に、素直に周りに相談していくことがとても大切なんだと思います。
「こんな合理的配慮があったよ」というものがあれば、コメント欄(最下部)で教えて下さいね。
また、「ここが分からないんだけれど…」とか質問等もあれば是非に聞いて下さい(笑)
それでは、最後まで読んで頂いてありがとうございました。
「PR」
、
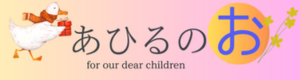
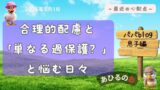
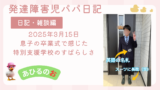

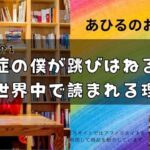
コメント