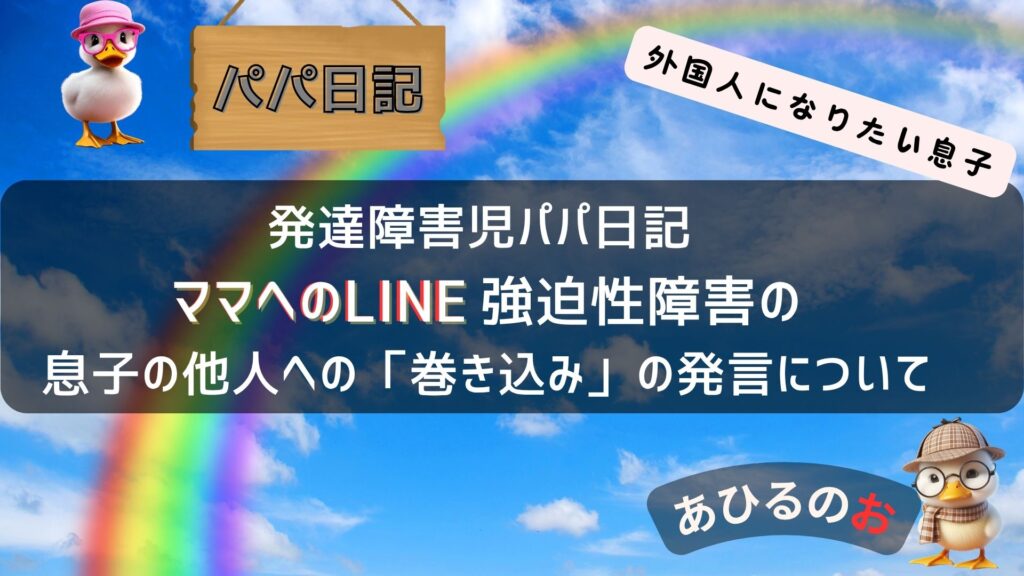
夜の12時。息子と話し合いをした。「今日も学校が嫌だった。先生が凄く悪いんだ。僕のことを外人と認めてくれないから、いじわるだ」と話し出した息子へ、注意をした。パパに注意されて、息子がどう捉えたかは分からない。解釈をする際の脳みその使い方が、僕らと違うと感じることが多い息子だ。だから、そう捉えているのかは分からない。
ママへの昨日のLINE 昨晩の体験記 強迫性障害への不安
以下はママへ送ったLINEです。(分かりづらいかもしれません。申し訳ないです)
「学校の先生が外国人と認めてくれないから嫌だ。先生が嫌いだから、暴れる。僕を理解してくれないから怒る」は巻き込み。(外人だと認めろという強制・命令)
これは、さっき注意した。
「自分で思うだけはいい。家族はいい。他人はダメ」と話した。
巻き込みがこれ以上広がるのは、怖い。「○○をしてくれないから嫌だ」は、今後先々、暗いものしか作らない。いつも、そういった他人が自分が望むことをしてくれないと、怒り出す。でも、自分は、人のいうことを一切守らない。言う事を聞かない。
強迫性障害について学ぶと、「支援」を考えさせられる
息子の将来をこの3年間で考える。
青い髪。
金髪。外国人になりたいという言葉だけで、
(ママは、こんな感じだよと)ネットで調べて見せているけれど、
そうではなくて、「それはどうかなあ?」くらいで濁さないと。
(息子には)「ルールが守れる」中で、自由を身につけさせないと。
ゆっくりで良いけど、それが彼の目標だよ、今は。
「外国人と認めてくれないから、嫌な日だった。あの先生は悪い人」
そんな考えで、生活介護やグループフォーム・作業所が継続できるんだろうか?
今後、福祉の支援を受けながら生きていけるのだろうか?
介護職の人は、そんな優しい人ばかりではないし、
「何言っているの?バカなの?」なんて簡単に言ってしまう介護職や支援員も必ずいる。
もう、あと3年。
他人への強要はだめ。
合理的配慮が勘違いを生み出さないように、彼(息子)を見つめ直さないといけない。
パパが嫌われ役になってでも、○ちゃんには伝えていく必要がある。
(色々話したあとに)最後に質問しなおしたら、
息子は「今は、そう呼ばないとダメかな。外人と認めないと嫌だ」にたどり着く。
知的障害があるのがネックで、その理解が出来そうで出来ない。自分の意見を曲げられない。
でも、他人への巻き込みは、酷くなったら、薬か入院(をさせるしかなくなる)。
息子の言うことに、「怒り出すと大変だから」というだけで合わせすぎたら、彼の強迫性障害や巻き込みは治らない。ママへの確認行動もエスカレートするだけ。
自分も反省。
息子に合わせ過ぎているね。
息子の部屋には、ぬいぐるみがありすぎだし、減らせない。「ぬいぐるみが汚れていないか」「なくなってないか」「勝手に階段に落ちていないか」それは物があればあるほど、不安が募っていく仕組みになっていて、より確認行動が増える要因になっているよね。
買わないと癇癪。
でも、物が増えれば不安・強迫観念に埋もれてしまう。
ママは、彼の確認行動で、疲れはてちゃうよね。
これじゃ、生活が成り立たなくなる。
何か手を考えないと。
○ちゃんの人生のために、おれ、奔走するから。
他人への巻き込みが許されるのは、18歳まで。
色々、調べて勉強する。
そのために、起業する。
最後は、パパがはるきを守る場所を作る
強迫性障害に関する分析:息子の行動から見る考察

一日たち、自分でこの文章を「強迫性障害」への家族の向き合い方として正しかったかどうかを再検証していきたいと思います。
✅強迫性障害(OCD)の特徴と「巻き込み行動」
- 強迫性障害とは、繰り返し浮かぶ不安(強迫観念)を打ち消すために、特定の行動(確認、洗浄など)を過剰に行う障害。
- 息子の「外人と認めてくれない先生が悪い」という思考は、「他人が自分の信念を受け入れないと不安になる」という 強迫的な信念に近い構造を持っています。
- 「家族はいい。他人はダメ」と制限しようとした僕の対応は、巻き込みの拡大を防ぐために必要なことと判断しました
✅巻き込みが激しくなるとどうなるか?
- 「他人も自分のルールに従ってくれないと嫌だ」「怒り出す」という状態は、強迫性障害の他者巻き込み型の典型。
- 本人の中では不安を軽減するための「確認」「同意の強要」ですが、周囲の疲弊を招きます(例:ママへの確認行動)。実際にうちのママは疲れ始めています。どうにか対応策を考えます。明日、医師に相談に行くように伝えました。
- このまま進行すると、社会生活(就労支援・福祉サービスなど)にも支障をきたすのではないかと心配です。医療からは、「息子さんの場合は、入院は効果がないと思います。余計に酷くなる可能性があります」と主治医から言われています。
✅物への執着・確認行動の意味
- 「ぬいぐるみが落ちていないか」「汚れていないか」という確認は、強迫的な思考と不安によるものだと考えてます。
- 所持物が増えれば増えるほど、対象が増えて確認行動が強化され、不安が強まるという 悪循環に入っているのだと思います。最初は、可愛いだけの部屋でしたが、今では不要なものまで捨てられない状況になっています。それが無くなっていないか?誰かが部屋に入っていないか?などの不安でいっぱいな様子です。
- 「買わないと癇癪」というのも、物が「不安を和らげる安全装置」になっているためと考えられます。欲しいものを見つけれると、それを購入するまで、しつこいくらい、おねだりしてきます。
今後に向けての支援の方向性
- ポイントは「不安の強さ」を和らげること。
- 対応例:
- 不安に直接付き合う(例:確認に応じる)→ ❌巻き込みが強化される
- 行動制限しつつ、本人の「我慢力」を育てる → ⭕中長期的な支援
- 合理的配慮は、「本人が成長できる環境づくり」であり、「全てを叶えること」ではないと捉え直すことが大切かもしれません。最近は、相談支援の研修で、合理的配慮を勉強しています。「合理的配慮をしないということは差別である」という考えがありますが、「合理的配慮」という言葉に埋もれて、完全にストレスをゼロにするくらい本人の意向に沿いすぎた結果なのではないか?と息子に申し訳ない心境にもなります。
まとめ:「これから」について
僕は、現状、不安の渦中にあります。
仕事を変えることにしました。相談支援の分野で働いていこうと決めました。それは、色々な事業所を知っていきたいという気持ちからです。それを成しえないと、息子の居場所を探せません。息子は、これまでに福祉から拒否されてきた過去があります。
僕自身は、息子を放デイで一時的に見てきましたが、決して難しい子ではありません。放デイでうちの息子を見ていくのが大変という事業所は、正直、前段階で「難しい」と判断しすぎなように思います。それは、心からの客観視です。そういった形で、拒否をされている子は、この世の中で沢山いるのだろうと思うと切ない気持ちになります。
僕自身は、相談支援を行いながら、息子の居場所を同時に探していこうと思っています。そして、将来は、どこにも行く所がなければ、自分がその居場所を作ろうと考えています。僕にとっては、とても高いハードルですが、障害児の父になったからには、そういった場所を作っていくことも、一つの役割のように感じます。
うちは、前にも後にも、息子が中心の家族です。
息子が落ち着いて、ニコニコした生活が出来れば、妻の心も落ち着きます。
そして、それが娘に帰っていきます。
そのために、僕がいつでも冷静で、全力の人間でなければならないのです。
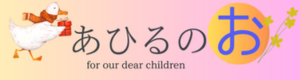
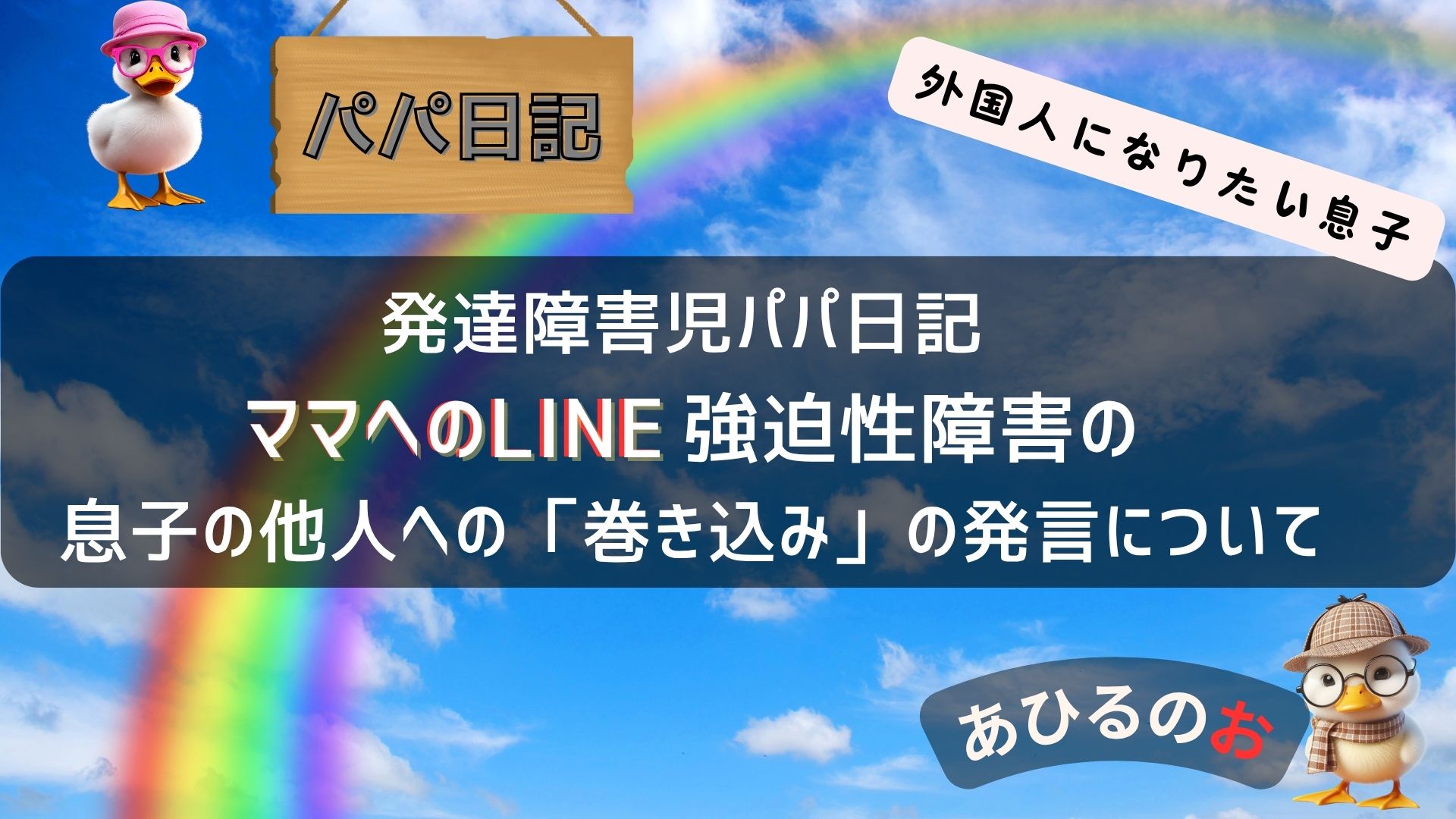

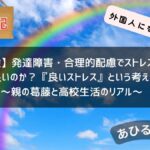
コメント
あひるのおさん、息子が苦手な鬼滅の刃とファミマがコラボしたので注意してください⚠️ ローソン前を通れなくなってしまったので2度同じ様なことが起こりません様に
https://l.smartnews.com/m-5N3LQLcs/WH2Ljh
コメント、ありがとうございます。鬼滅の刃のコラボが凄いことになりそうですね。教えて頂いてありがとうございます。「夏休みは一切でかけない」と息子は訴えてきてまるね。色んな面で不安が大きくなっているようです。強迫性障害が強くならないように…と僕らも慎重になっちゃいます。
息子が最近不安が強くなってきているらしいので少しでも不安を軽減する考え方を作りました。
⚫︎ 鬼をソニックやペガサスがやっつける妄想
⚫︎ 負の感情で操るミラキュラスの悪者ホーク・モスにアクマタイズ(洗脳)されないよう感情をコントロールする考え方
⚫︎不安になってきたら楽しいことを見つけて不安な事を忘れる考え方
(私が実際に実践した方法)
あひるのおさん、この考え方はどうでしょうか?
うちの子は、今は、学校も嫌だし、外出も嫌だしという状況ですが、あえてそれを言って「パパがどんな反応をしているか」を見ているような所もあります。高校1年生ですが、脳内は、まだ10歳くらいかな?と感じることが多いです。不安はずいぶんと強くなってきていますが、夏休みは、僕が一緒に過ごすつもりです。三番目の考え方がとても良いですね。良いことで気持ちを埋めることが一番の幸福をあげるコツのように感じます。ありがとうございます。意識的に実践してみますね!(感謝)